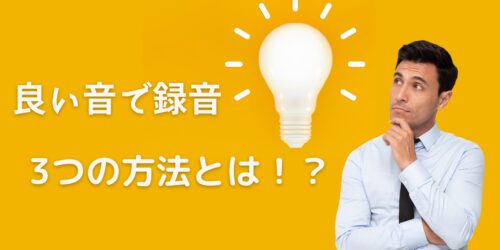ステレオ録音のセッティング方法とワンポイント録音のススメ

この記事の目次
ステレオ録音とワンポイント、ステレオペア録音について学べます。
よりアカデミックに学びたい方は”【保存版】ステレオペアレコーディング完全ガイド”という記事がありますので、是非そちらもチェックしてみてください。
より具体的な接続方法などを紹介しています。
- ステレオ録音のやり方がわからない。
- 録音したいけどどうやっていいかわからない。
- マイクを買ってみたけどどうやって置いたらいいかわからない。
ステレオ録音ができると強い
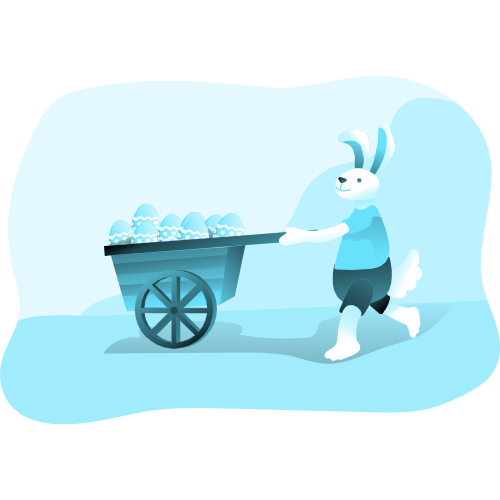
さて、ステレオ録音はどういったシーンで活用すればいいのでしょうか?
これは主に(ステレオペア録音)ワンポイント録音でその真価を発揮すると考えます。
ワンポイント録音とは、厳密に言うと指向性XY方式のステレオペアマイクになります。
大丈夫!あとで解説します!
筆者は無指向性のワンポイント(ステレオペア録音)を主に採用しているわけですが
これは無指向性マイクロフォン2本のみを使ったシンプルな録音方式で
セッティング自体は簡単ながらもわずか1cmでも高さがずれたり、場所が変わると大きく音質が変化してしまう非常に奥ゆかしい録音方法になります。
やはりステレオ録音ができると一気に世界が広がります。
ステレオ録音のさらに高度な技術になると、VR録音というものが出てきます。
ステレオ録音、バイノーラル録音、VR録音はそれぞれ全然違う録音方式なのでここではとりあえずこの有名な3つは別物!ということだけしっかり覚えておいてください。
SENNHEISER ( ゼンハイザー ) / AMBEO VR MICちなみにVRマイクは対応しているレコーダーじゃないと録音できないので注意してください。
今のところ国産レコーダーでVRマイクに対応しているのはZOOM F6がおすすめです。
ZOOM ( ズーム ) / F6 +専用プロテクティブケースPCF6セットステレオワンポイント録音をマスターするメリット
ではこの奥ゆかしいワンポイント録音方式をマスターするとどんな良いことがあるんでしょうか?
ズバリ!
一匹狼になれる!
という点です。
企業よりも個人と言われる昨今、フリーランスとして活動していくためには、レスポンスの速さはもちろんですが、やはり小回りの良さが求められます。
マルチトラック録音(じゃがりこ飯マスタリングが必須)で勝負する場合、例えばオーケストラの収録などのお仕事があった場合は、一人で現場にいって収録するなんてことはまず不可能です。
最低でも10人ほどバイトスタッフを調達しなければいけません。
これではクライアントにとってももちろん予算が跳ね上がりますし、お仕事を構成するのにも日程調整やその他たくさんの雑務が増えてしまいます。
企業であれば対応可能となりますが。
しかし、ワンポイント録音であれば、マイク2本とレコーダー持っていけば一人で録音可能。
音質やクオリティーは変わらず、もしくはそれ以上の可能性を秘めたワンポイント録音ですが、数十人規模のスタッフが必要な収録を一人でこなすことができます。
Vlogなどの撮影でも別途スタッフを雇う必要がなくなります。
じゃあなんでみんなワンポイント録音にしないの?!
これもズバリ言ってしまいましょう。
言いにくいけど言ってしまいましょう。
理由の一つとなるのが・・・
見栄えが悪いから。。。
見栄が悪いってどういうことだよ。。。
説明します。
数十人のスタッフが必要なマルチトラック録音も、マイク2本だけもってやってくるワンポイント録音のエンジニアももちろん音響のスキルは同じ。
そしてかける知的労力も同じ。
しかし・・・クライアントからみると・・・
本番中もインカムを使い随時セットしたすべてのマイクのゲインを確認。
本番始まるちょっと前に録音ボタンを押して、ヘッドホン越しに楽しそうに鑑賞している。
当然状況Aの方が見栄えが良いですよね。
そりゃクライアントからすれば、状況Aの方が予算をたくさん出した甲斐があるってもんです。
なので状況Bの場合は心配がられます。
収録後に値下げ交渉されることもあります。
「〇〇してただけだからもう少し安くなりませんか?」
などなど。
こういう事情があって、なかなかワンポイント録音は流行らないし、仕事の依頼があっても無駄にマイクたくさん立てたりするエンジニアもいます。
結局使うのはステレオペアだけなのに、使わないトラックを見栄えのために並べるということもしなければいけません。
実際本当にやります。
これは昨今のカメラ、映像の世界でも同じだと思います。
手のひらに収まるサイズの素晴らしいカメラがたくさんあります。
フリーランサーの方でも写真や映像の依頼があった場合、そのままだとクライアントに舐められる・・・
だから見栄えよくするために必要のないRigまでつけてゴツ盛りのフル装備にする。
巨大なカメラと装備を持っていくだけで「さすが、プロの機材は違いますね!」と言われるんですね。
本当はSonyならa1と本気のレンズ一本だけで最高の仕事ができるのに・・・です。
そして難しい
ワンポイント録音はじゃあ簡単か?
と言われれば、はっきりいって難しいです。
マルチマイクでいろんなところを保険で録音しておく手法の方があとから潰しが効きます。
ワンポイント録音は現場で音を作ってしまわないといけないので後から潰しが効きにくいのも特徴なのでかなり緻密なモニター環境と、ミックスルームでモニターするほどの集中力が要求されます。
テクノロジーのおかげ
当然ワンポイント録音が一人で完結するのはテクノロジーのおかげです。
優秀なADCやマイクアンプが手のひらサイズのレコーダーに凝縮され、テープはメモリーカードに。
軽くても丈夫なマイクスタンドケース。
録音の分野もまたテクノロジーの進化の恩恵で小回りの効く立ち回りができるようになったと言えます。
ステレオペアの各方式を覚える
さて、これは突き詰めると結構な種類のセッティング方式が存在しています。
しかし、基本的に覚えるのは二種類で大丈夫。
でも一応教養のために何種類か紹介しておきます。
指向性のステレオペアと無指向性のステレオペアのセッティング方式をそれぞれ一種類づつマスターしていきましょう。
無指向性マイク:AB方式

AB方式は2本の無指向性マイクを一定の感覚で平行に並べてセットします。
一般的には30cm〜60cmの間で良いポイントを見つけます。
オンマイク気味の収録で使うことが多いですが、もちろんオフマイクでもばっちり昨日します。
オーケストラの収録では釣りマイクが各ホールに設置されています。
この釣りマイクはAB方式のホールが非常に多いです。
録音や音響にこだわりのあるホールでは、デッカツリー方式やフィリップス方式が採用されたりしています。

こちらは金田式電流伝送DC録音でのコンサートホールでのテストの際の写真です。

この時の実験ではデフォルト時よりもかなり低めに設定していました。
無指向性マイクでのステレオペア収録ではこのAB方式が基本になると考えて差し支えないでしょう。
ホールを借りても釣りマイクをこのように交換させてもらえるかどうかは交渉次第で基本的に9割くらいは断られるのでホールでのAB方式で収録したい方は根気よく対応可能なホールを探すか、まずは関係者の人脈作りに勤しみましょう。
Kotaro Studioの出す暫定的な幅
もちろん環境によって様々だとは思いますが、よほどのことがない限りこの数値でマイクの間隔はセットし、あとはステレオペアで座標を動かしながら音を探っていきます。
興味があればKotaro Studioがお届けする「音楽家育成塾」の音響関連記事を参照してください。
指向性マイク:NOS方式
無指向性マイクの場合はAB方式でほぼ一択でしたが、指向性ステレオペアの場合はいくつかあります。
今回の記事では代表的なものを紹介。
まずはNOS方式、通称オランダ方式をマスターしてください。
こちらはオランダ放送協会が開発したステレオペア録音方式となっており、簡単に設置できるので世界的にもかなり普及しています。
特にこだわりがなければ指向性マイクのペアはこのオランダ方式でOK。
写真はKM184を使ったオランダ方式の様子ですが、こちらは間隔は守っておらず若干独特のスタイルになっていますが、形としてはこのような形式になっていきます。

NOS方式はノイマンのKM184などのペンシルタイプのマイクロフォンが使われることが多いですが、大口径マイクでもセッティング可能です。
筆者はLCT540のステレオペアや、PCM-1のステレオペアといった大口径マイクでのNOS方式のセッティングもよく使います。
指向性マイク:ORTF方式
通称フランス方式。
このフランス方式も教養の一つとして覚えておくと損はないかと思います。
フランス方式は、2本のマイクの角度を110度に設置。
【上級者向き】チェロや弦楽器の録音方法〜ORTFとAB方式をミックスするマイクセッティング
素子の間隔は17cmとかなり窮屈なセッティングになっています。
参考写真は用意できませんでしたが、このセットだとマイクケーブルなどが干渉しあったりしてうまくセッティングできなかったりするので、最初からこのフランス方式で収録するための専用マイクなどが発売されています。
真っ先に出てくるのはやはりショップスでしょうか。
SCHOEPS MSTC 64 Uはフランス方式での録音専用マイクロフォンとして有名です。
紹介ページを貼っておくの形状に注目してみてください。
指向性マイク:XY方式
こちらも覚えておくといいかもしれません。
こちらは指向性マイクとしては定番のセッティングにはなります。
ただ個人的にはXY方式の音がどうにも合わずに、好きになれずにいます。
入門機〜中級機種のハンディーレコーダーなどに内蔵されているマイクはこのXY方式で構成されているものが多いです。
例えば、タスカムのDR-40XなどはAB方式とXY方式を切り替えて使えるという特徴がありますよね。
TASCAM DR-40X 内蔵マイク VS 外部マイク 音質チェック
2本のマイクの素子の間隔は0cmにします。
0cmなので上下に重ね交差して置くのが特徴的です。
こういったコンパクトなセッティングが可能なのでレコーダーの内蔵マイクとして採用されるわけですね。
2023年時点ですと、ZOOMから発売されているM4などにもXYマイクが搭載されており、素子の口径も大きなものになり音質も素晴らしいものになっています。
【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit ステレオリンクの問題点
この他、デッカが開発したデッカツリー方式や、フォリップス開発のフィリップス方式などがありますが、結構マニアックなので、こちらも需要がありそうならマスター講座でお届けしたいと思います。
重要なことは、あなたのオリジナルセッティング方式を確立してしまってOKということ。
この方式で録音しないといけないという決まりはありません。
実際には十字架でセットする人や、ちょっとずらして二重にセットする人など様々で、それぞれに面白い音響となっており、自分なりの音響を探る旅も面白いですよね。
カメラのライティングと同じです。
ある程度のセオリーはありますが、決まりはなく、あなた自身の表現を何より最優先にしてください。
セオリーはお仕事で失敗しないための知識として覚えておきましょう。
基本軸に囚われすぎない

音響の世界に正解はありません。
正解を決めるのは常にあなた自身です。
これら紹介した方式は誰かに伝えるため、シェアするために決められた間隔と距離であり、すべての音源に対して常に最高の結果を残してくれるものではありません。
筆者の出したAB方式の数値も必ず毎回その数値というわけではありません。
筆者がピアノを収録する時は30cmを下回る間隔でセットするように、あなた自身のオリジナルの方式を作ってもらって何も問題ありません。
それがいい音であれば、それが正解です。
まずはセットしてみる。
そしていろんな音を撮ってみる。
無指向性はAB方式、指向性はオランダ方式・・・
を当サイトでは推奨していますが、フランス方式以外考えられない!という意見もまた正解です。
いろいろ試してみてあなただけの正解を見つけてみてください。
関連記事もいかがでしょうか?
Kotaro Studioではオーディオや音響に関する初心者向けの記事から、より専門的な音響に関する記事まで幅広くお届けしています!