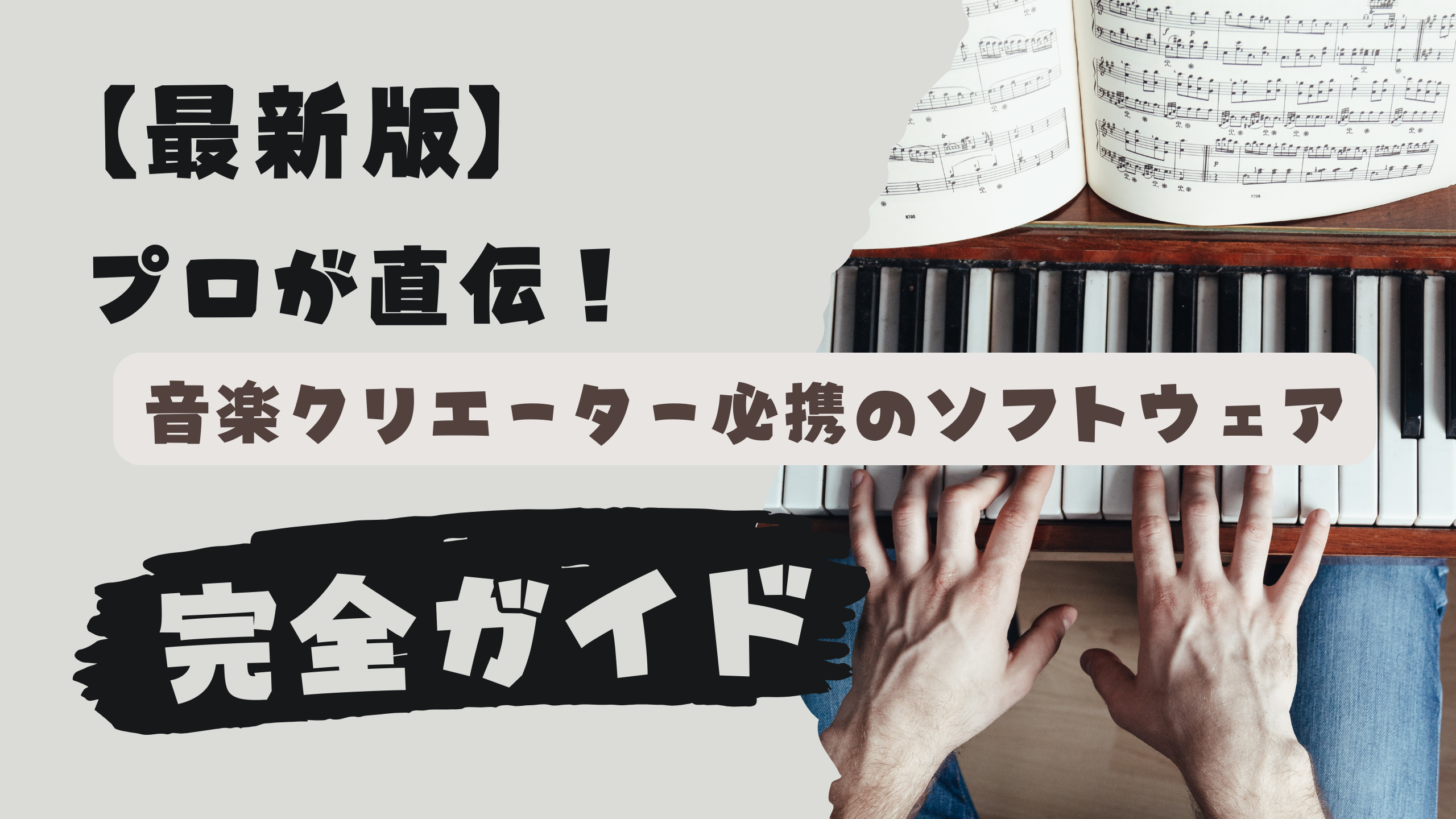【保存版】聴き比べあり〜マイクケーブルのおすすめと選び方

この記事の目次
マイクケーブルっていっぱいあってどれを買っていいかわからない。
そんなお悩みを抱えている方。
この記事を読めば購入するべきマイクケーブルが一発でわかります。
当スタジオの音響顧問である金田式DC録音の五島昭彦氏推薦のケーブルですので、音質は折り紙付き。
五島昭彦推薦ケーブル

いろいろ試してみた結果モガミの2549が一番音がいいとの推薦をいただいています。
筆者の個人的にもこのケーブルに変えてから音が明確に違っています。
後半で聴き比べを用意していますので、是非その違いを体験してください。
MOGAMI ( モガミ ) / 2549 XLRM-XLRF 3m をサウンドハウスでチェックサウンドハウスさんでは完成品は3mと5mですが、amazonでは0.5mが売られていました。
マイクケーブル選び3つのポイント
基本的には上記の2549を購入するのがベストですが、なんらかの理由で買えなかったり、他のも試してみたいという方は次の3つのポイントを意識してみてください。
1、プラグはNEUTRIK(ノイトリック)を選ぶ
NEUTRIK(ノイトリック)は信頼できるパーツメーカーです。
NEUTRIK(ノイトリック)以外のものはどんな音になるのかわかりませんので、注意してください。
2、長さをしっかりチェック
大は小を兼ねるといっても、自分が収録、使用する現場の状況をよくイメージして3m、5m、10mと選んでいくようにしてください。
筆者がamazonで購入した0.5mはあんまり使わない長さかもしれませんが、やはり状況によっては必要です。
また、10mなんて長いの使うことはない!と思っていても使うことはあるのでお仕事で録音をしていこうと考えている方は是非1セット持っておいてください。
10m以上は高額になってきますので、クラシックプロのものがおすすめ。
クラシックプロのマイクケーブルは余計な加工がされていないため、かなりストレートに素直な音になります。
CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / MIX100 マイクケーブル 10mをサウンドハウスでチェック3、カラーを使い分ける
これは結構見落としがちで大切なポイントです。
黒は舞台上では確かに便利ですが、カラーによって使い分けたり配線したりすることは現場の混乱を防ぐことにもつながりますし、実際撤収の効率は格段に上がります。
オーディオケーブルは基本的にMOGAMIのものを選べば間違いは起こりません。
聴き比べ
とはいえ実際に聴き比べないとわからないところがありますよね。
例によってポッドキャスト向けなのてモノラルではありますが、クラシックプロのものとモガミのケーブルを聴き比べてみましょう。
環境はザイドのPC-M1にサウンドデバイスのマイクアンプ、ZOOM F3のADCを使用しています。
クラシックプロの音
比較しなかったらクラシックプロのマイクケーブルでも充分な音質が得られるかと思います。
モガミ2549の音
圧倒的なシルキーさ、絹のような透明感、気品高い印象を受けますよね。
モガミを聞いてからクラシックプロを聞いてしまうとクラシックプロが荒々しく聞こえてしまいます。
価格差を考えると7倍や8倍程度しますが、音質に対する恩恵は10倍以上?あるかと思います。
一度モガミの音を聞いてしまうともう戻れないですね。
おしゃれもオーディオも足元から
音や音質に悩み続けている人に多いのが、マイクはいいものを買ったんだけど、マイクアンプやレコーダーは適当なのを使っているというものがあります。
また、マイクアンプやレコーダーもしっかり選定したんだけど、マイクスタンドをけちってしまうとか、今回のようにマイクケーブルを適当なのにしてしまうなどがあります。
オーディオは視覚アートではありません。
マイクロフォンだって本来見えない存在。
もっともっと見えないところへの気遣いや配慮が、音質をよくしていきます。
マイクケーブルは音を伝達するための大切な道です。
例えるならできたてほやほやの美しいアスファルト(マイクケーブル)を整備されたスポーツカー(マイク)で走るようなもの。
整備されたスポーツカーでオフロードを走ってもスポーツカーの魅力や性能を発揮できないのと同じです。
道もちゃんと整備してください。
みなさんの素敵なオーディオライフのために!