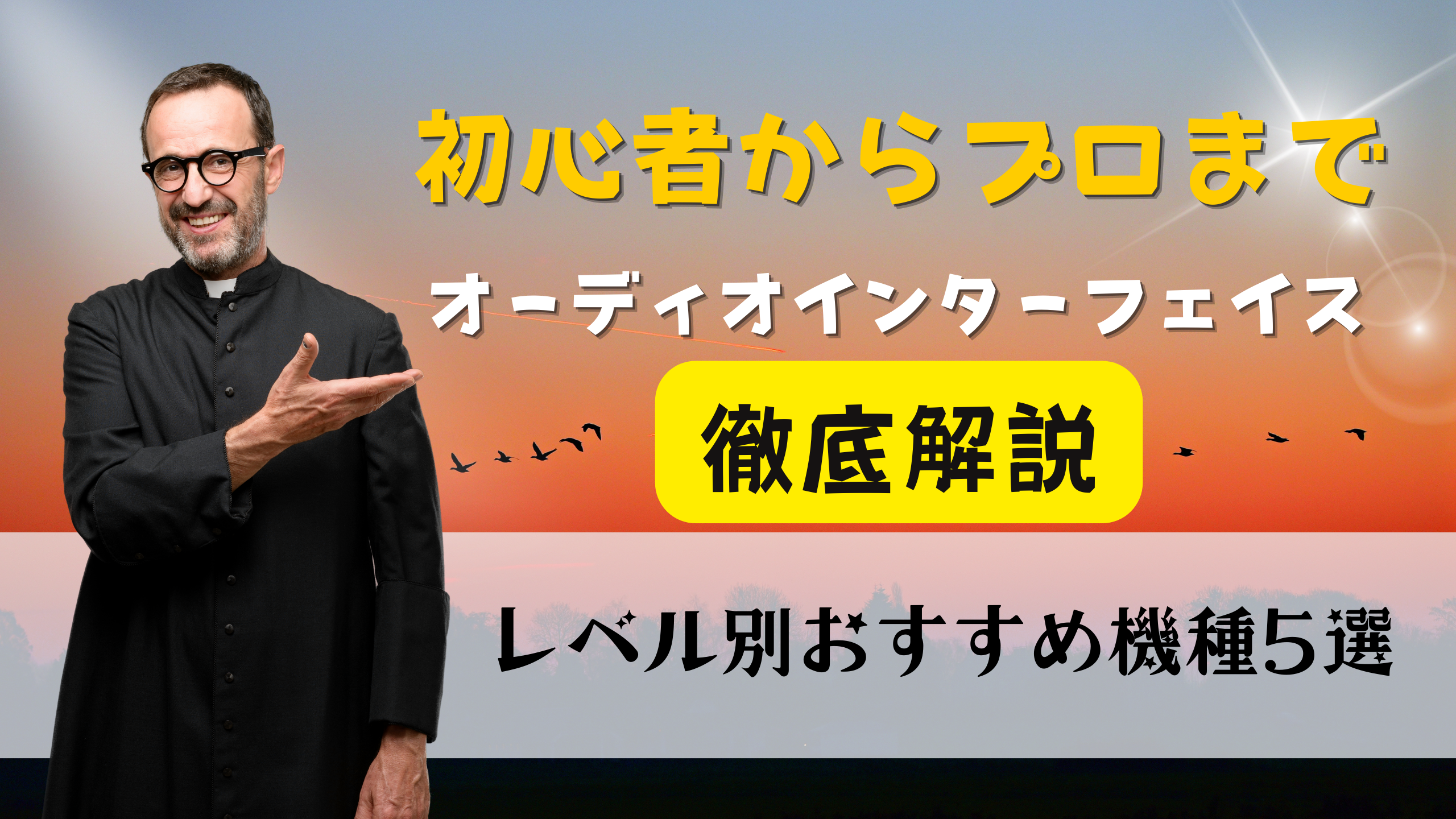【保存版】ステレオペアレコーディング完全ガイド

この記事の目次
これまでモノラル録音しかしてこなかった方、またそもそもモノラル録音とステレオ録音の切り替え方法を知らなかった方、この記事をきっかけにワンランク上の音質にアップグレードしてください。
ステレオペアレコーディングは、リアルな音響空間を捉えるための重要な技術です。
この記事では、ステレオペアレコーディングの基本原則とそのメリットを探求します。
現在ポッドキャストの音質向上に躓いている方や、もう一歩先の音質を手に入れたい方は是非最後までお付き合いください。
あなたにとっての解決の糸口が見つかるかもしれません。

簡易紹介:こうたろう
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
その後金田式DC録音のスタジオに弟子入り
プログラミング(C)を株式会社ジオセンスのCEO小林一英氏よりを学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門のピアニスト、またスタジオでは音響エンジニア、フォトグラファーなどマルチメディアクリエーターとして活動中
当記事ではプログラマー、音響エンジニアとして知識とスキルをシェアしていきます
ステレオペアレコーディングとは何か?
ステレオペアレコーディングは、二つのマイクロフォンを使用して、音源の立体感と空間感を捉える録音技術です。
この方法は、聴取者により自然でリアルな聴覚体験を提供することを目的としています。
ステレオペアレコーディングの基本原則
ステレオペアレコーディングの成功の鍵となるのが、マイクロフォンの選択、配置、角度です。
後述しますが、機材選びもとても重要になってきますので、購入はもうちょっと待ってくださいね!
適切なマイクロフォンの配置というのは、録音される音源の種類や環境によって異なり、現場の数だけマイキングが存在します。
そのコーディネート力が録音エンジニアの腕の見せ所!
一般的にはXY法、AB法、ORTF法などがあります。
ステレオペアレコーディングの技術と応用
ステレオペアレコーディングの技術は多岐にわたり、それぞれに特徴と適用シーンがあります。
このセクションでは、これらの技術を詳しく解説し、どのようなシチュエーションで最適かを考察します。
ステレオマイキング技術の種類
ステレオマイキングには、一般的にXY法、AB法、ORTF法、デカツリー法など、様々な方法が存在しており、考案者の名前がついたオリジナルのセッティング方法もあるほどです。
これらの技術は、マイクロフォンの配置と角度によって異なる音響効果を生み出します。
XY法とAB法の比較
XY法は指向性マイクロフォンを一定の角度で交差させることで、一点からの音源を立体的に捉えます。
多くのハンディレコーダーで採用されている方式で、俗にいうワンポイント録音とは指向性XY方式のことを指します。
多くのハンディレコーダーで採用されている理由が、素子の性能による差を感じにくい点と、2本のマイクを交差させるため、セッティングに幅を取らないというところ。
一方、AB法は無指向性マイクロフォンを離して配置し、より広がりのあるステレオイメージを作り出します。
AB方式は30cm〜1mまで幅広くレンジがあり、エンジニアによっては1m以上の幅を取ることもあります。
各マイクロフォンの距離や、特にピアノ録音のAB方式の距離の取り方は明確なcmまで記載音響講座を参照してください。
ORTF法とデカツリー法
ORTF法は、マイクロフォンを特定の角度と距離で配置し、自然なステレオイメージを作り出します。
デカツリー法は、特に大規模なオーケストラや合唱団の録音に適しており、豊かな音響空間を捉えることができます。
ステレオペアレコーディングの応用分野
ステレオペアレコーディングは、コンサート録音、映画のサウンドトラック制作、野外録音など、多様な分野で活用されています。
それぞれの分野で求められる音質や音響効果に応じて、適切なステレオマイキング技術が選ばれます。
ステレオペアレコーディングの機材選び
ステレオペアレコーディングにおいて、適切な機材の選択は非常に重要です。
このセクションでは、優れた録音品質を実現するためのマイク選びのポイントと、レコーダーやアクセサリーの選び方について解説します。
マイク選びのポイント
マイク選びでは、録音する音源の特性と録音環境を考慮する必要があります。
指向性、周波数特性、感度など、マイクの仕様を理解し、目的に合ったものを選ぶことが重要です。
また、録音する音楽のジャンルや楽器ごとにも最適なマイクロフォンは違ってきます。
Kotaro Studioでは長年の経験から導き出したマイク選びのポイントが各楽器ごとにありますので、是非関連の記事も参照してください。
レコーダーとアクセサリー
高品質なレコーダーは、クリアでバランスの取れた録音を実現します。
また、ショックマウント、ウィンドスクリーン、スタンドなどのアクセサリーも、プロフェッショナルな録音には欠かせません。
レコーダー選びのポイントは常にマイクアンプを軸に考えること。
ADCは昨今ではだいたいどこのレコーダーも同じチップを採用していることも多いので、マイクアンプ性能に意識を向けるべきです。
マイクアンプ選びに失敗すれば取り返しがつきません。
逆にヘッドホンアンプは後からどうにでもなります。(もちろんヘッドホンアンプも素晴らしいものに越したことはありません。)
マイクアンプの優れたレコーダーは何も高額なプロ仕様のものでなくても存在しています。
その一つがこちら。
ただしタスカムのレコーダーがいつも優れたマイクアンプを提供していると過信するのはやめてください。
レコーダーやマイクアンプ選びにお困りの方は、こうたろうのDMまで気軽にメッセージしてくださいね。
ステレオペアレコーディングの実践例
ステレオペアレコーディングは理論だけでなく、実践を通じてその真価が発揮されます。
このセクションでは、音楽ライブや野外での自然音録音など、具体的な実践例を紹介し、それぞれのシチュエーションでの録音テクニックを探ります。
音楽ライブのレコーディング
音楽ライブのステレオペアレコーディングでは、会場の音響特性と観客の存在を考慮する必要があります。
観客の存在というのはなにもノイズに関してだけではありません。
夏か冬か?で大きく音響が変化することを理解してください。
夏の衣服は薄く、そこまで音を吸いませんが、冬の衣服はアウターは預けているとはいえ、セーターなど音を吸収する素材が多く、反響や残響に関して考慮したマイクセッティングが必要になってきます。
マイクの選択と配置が、ライブの雰囲気を捉える鍵となります。
野外での自然音録音
野外での自然音録音は、環境音のリアリティを捉えるためにステレオペアレコーディングが効果的です。
風の音、鳥の声、水の流れなど、自然のサウンドスケープを生き生きと記録するために重要なのがウインドスクリーンの存在です。
野外では風対策が最重要課題となります。
ステレオペアレコーディングの歴史と進化
ステレオペアレコーディングは、長い歴史を持ち、技術の進化と共に変遷してきました。
このセクションでは、ステレオ録音の歴史的背景と、時代と共に変わってきた技術の進化に焦点を当てます。
ステレオ録音の歴史的背景
ステレオ録音の歴史は、20世紀初頭にその起源を見ることができます。
最初のステレオ録音の試みは、1931年にアラン・ブラムレインによって行われました。
彼は、二つのマイクロフォンを使用して、音源の異なる位置から音を捉えることに成功し、これがステレオ録音の基本原理となりました。
第二次世界大戦後、ステレオ録音技術は大きく進歩しました。
ヒトラーの演説をより明確に拡散するために、今なおオーディオ業界のトップに君臨するゼンハイザーやノイマン等のオーディオメーカーが一気に進化しました。
1950年代に入ると、ステレオレコードが市場に登場し、音楽業界に革命をもたらします。
これにより、リスナーは家庭でオーケストラの演奏を、まるでコンサートホールにいるかのような臨場感で楽しむことができるようになりました。
ステレオ録音技術の発展は、マイクロフォン技術の進化と密接に関連しています。異なる指向性を持つマイクロフォンの開発により、より精密で多様な録音が可能になりました。また、マルチトラックレコーダーの導入によって、録音の柔軟性が大きく向上し、音楽制作の幅が広がりました。
1960年代には、ステレオFM放送が開始され、ステレオ録音の普及がさらに進みました。家庭用のステレオシステムが広く普及し、高品質な音楽体験が日常的なものとなりました。
デジタル時代の到来とともに、ステレオ録音技術はさらなる進化を遂げました。
デジタル録音と編集技術の発展により、よりクリアで精細な音質が実現し、音楽制作の可能性は無限大に広がりました。
現代では、ステレオ録音は音楽はもちろん、映画、テレビ、ラジオ放送、さらにはインターネット上のコンテンツ制作においても不可欠な技術となっています。
ステレオペアレコーディングのトラブルシューティングと解決策
ステレオペアレコーディングは、時に技術的な問題に直面することがあります。
このセクションでは、一般的なトラブルとその解決策を、実例を交えて解説します。
一般的な問題とその対処法
フェーズの問題は、マイクロフォンの配置が原因で発生することが多いです。
これを解決するには、マイクロフォンを同じ距離に配置し、向きを調整することが重要です。
また、ノイズの問題に対しては、高品質のケーブルの使用や、電源のハムノイズを避けるための適切な電源管理が効果的です。
多くの場合下記の記事に記載されているトラブルシューティングで解決することが多いので、ノイズ等でお悩みの方は是非参照してください。
高度なトラブルシューティング
より高度なトラブルシューティングでは、録音環境の最適化が鍵となります。
例えば、部屋の反響やエコーを抑えるために、吸音材を使用することが有効です。
また、機材のキャリブレーションを行い、マイクロフォンやレコーダーの設定を最適化することで、よりクリアな録音を実現できます。
具体的なセッティング方法
ここからは具体的なセッティング方法についてみていきましょう。
まずは指向性マイクロフォンを使ったオランダ方式でのセッティング事例をみてみましょう。
オランダ方式では二つの素子の角度が大切になってきますし、指向性マイクだけにその方向と角度は音質に大きく影響します。
一般的にはペンシル型マイクでセッティングする事例が多いです。
例えば有名なマイクだとKM184などはこのオランダ方式でのセッティングは最高の音がでます。
NEUMANN / KM184の価格比較
ただし、指向性の大口径マイクでもオランダ方式でセッティングすることは可能です。
例えば今は中古でもかなり入手しにくくなりましたが、SEIDE PCM-1という大口径指向性マイクは筆者が愛用している指向性大口径の一つですが、このようにオランダ方式でセットすることが可能です。
ポイントはショックマウントごと距離を適切に取り、マイクロフォン本体の向きを変えて適切なオランダ方式を作り上げること。
うまく理想のステレオ感がでる位置でステレオペア録音してください。

ステレオペアリンクの設定
多くのレコーダーでは、ステレオペアリンク設定というものがあります。
この設定をしないと、LとRで別々のモノラルトラックとして収録されてしまいます。
LとRがあるということはほぼ必ずステレオ設定が可能になります。
ほぼ必ずというのは、過去に一度だけ稀有なケースをみたことがあり、ZOOM M4でした。
この機種は素晴らしいコンセプトのレコーダーでしたが、外部入力が左右に分かれているにもかかわらず、ステレオペアリンクができないままのリリースとなっていました。
筆者がZOOMの技術部の方と話したところ、アップデートにて後日ステレオリンクの問題が解消されたという歴史があります。
稀にこういったことも起こるのでほぼ必ずという言い方をさせていただきました。
 【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数
先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。
【M4 MicTrakレビュー】 M4 32bit 参考音源多数
先入観なし、忖度なしにお届けしていきます。作例などもいろいろ用意していますので是非最後までチェックして購入の際に参考にしてくださいね。
ステレオマッチドペアについて
ステレオペア録音するには(通常)マイクロフォンは2本必要になります。
では同じものを2本買えばいいのでしょうか?
答えはYES.
基本的にマイクロフォンでステレオペア録音する場合は、同じマイクを2本購入することで実現できます。
ただし、ステレオペアマッチというモデルがあるんです。
DPAやノイマンなどのフラッグシップマイクをリリースしている会社に多いのですが、こういったマッチモデルは、専用の測定器にてゲインの測定をしっかり行なっているので、安心して使うことができます。
また、ペアマッチしていなくても2本購入できるマイクロフォンメーカーがあります。
それがルイット。
当スタジオも大好きなオーストリアの新興オーディオメーカーで、ルイットのマイクは本当に素晴らしいものが揃っています。
そのため、同じ型番のマイクロフォンであれば、違うお店で購入しようと中古で購入しようと安心というわけです。
とはいえ、中古のPCM-1でステレオペアマッチで録音しているように、通常はそこまで厳密に神経質にならなければ製品化されているマイクは問題ないことの方が多い気がします。
筆者がたまたま運が良かっただけかもしれませんが・・・・
L, R / 1, 2接続方法
ステレオペアリンクでの録音では、通常、マイクや録音機器に”1″と”2″、または”L”(Left: 左)と”R”(Right: 右)というラベルがついています。
これらはステレオ録音における左右のチャンネルを指します。
左側のマイク(自分から見て左)は”L”または”1″に、右側のマイク(自分から見て右)は”R”または”2″に接続します。
したがって、自分がリスナーの位置にいると想定した場合、Lは自分の左側、Rは自分の右側になります。
ただし、特定の録音環境やアーティストの要望により、標準的なL/R割り当てを変更することもあるので柔軟に対応してください。
ステレオペアレコーディングの未来展望
ステレオペアレコーディングの未来は、新しい技術の導入とクリエイティブな発想によって形作られています。
3Dオーディオ、バイノーラル録音、AIによる音響分析など、これらの新しい技術がどのようにステレオペアレコーディングを変革していくかを探ります。
ステレオペアレコーディングの将来性は、新しい技術の採用だけでなく、それを活用するクリエイターの創造力にも依存します。
例えば、バーチャルリアリティや拡張現実感を伴うコンテンツ制作において、ステレオペアレコーディングは重要な役割を果たすでしょう。
これらの新しい分野での応用により、ステレオペアレコーディングはさらに進化し、多様な音響体験を提供することが期待されます。