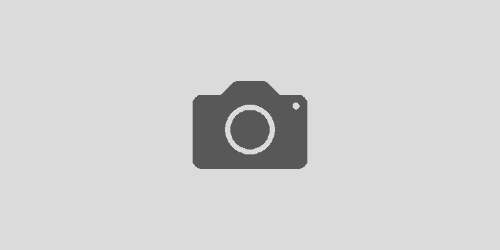じゃがりこ飯的マスタリングとは?

この記事の目次
本日はいよいよ音響の真骨頂!?
とはいっても、とりあえず音響ができるようになるのが目的としており、本格的なマスタリングの方法を伝授するわけではありません。
『そもそもマスタリングって何?』という部分からマスタリングのやり方をやさしく見ていきたいと思います。
この記事は広告リンクを含みます。

簡易的に使えるスキルだけピックアップしました!
そもそもマスタリングって何?
さて、映像関係の方やミュージシャンの方が苦労するのがこのマスタリングというイメージがあるかと思います。
そもそもマスタリングって何なんでしょうか?!
それは、ズバリ、「マスターテープ」を創る作業と言えます。
デジタル世代の方にはなんのこっちゃさっぱりわからない存在であるマスターテープ。
デジタルソフトでの編集も「はさみツール」なるものがありますが、マスターテープ作成時代のアナログ全盛期、リアルにはさみでテープを切っていたんです。
切る場所間違えたらそこでおしまい。
当たり前ですが、コントロール+Z(一つ前の作業に戻るショートカットキー)で復元はできません。
CDの時代
CDの時代になると、このアナログ時代のマスターテープの役割を果たすのがDDPファイルでした。
このDDPファイルというのがマスタリングソフトでしか作成できないファイルであり、DAWには備わっていないため、CDを制作する側の人はわざわざマスタリングソフトを設備投資として導入しなければいけませんでした。
ちなみにCD時代でもこのDDPファイルを取り扱えるのは、CDをプレスする工場と、工場を仲介する仲介業者と、マスタリングエンジニアくらいで、オーディオマニアですら取り扱うファイルではありませんでした。
じゃがりこ飯的マスタリング?

さて、昔テレビ番組の企画で、一流シェフにコンビニだけで買えるモノでどれだけの料理を作れるか?
一流のシェフはじゃがりこだけでどんな料理を作るのか?
などの企画があったりしました。
じゃがりこ飯というそうで、ネット上でもじゃがりこ飯のレシピが大量に出てきます。
ココナラなどでフリーランスの音響エンジニアがマスタリング(ミックスなども)を承りますというお仕事依頼があるかと思いますが、ああいった作業はまさにこのじゃがりこ飯なわけです。
- スマホの録音アプリで録ったんだけどなんとかならないか?
- カメラの内蔵マイクだけど音が悪いからなんとかならないか?
- 裁判の証拠に使いたいんだが、ノイズがひどくてなんとかならないか?
こういった依頼が実に多く、現代のフリーランスが受けるマスタリング依頼の3割くらいがこういったコンビニ素材を高級料理っぽく変えてくれ!という依頼だったりします。
最高の料理はシェフが食材を調達する
さて、最高の逸品であれば料理は感性だけで完成します。
音響も同じで、しっかりした素材を用意すれば現代のマスタリング作業はほぼ整えるだけで済んでしまいます。
例えば、筆者が過去実際に受けた依頼に、「カラオケを流しながら楽器演奏したものをスマホで録音したんだが、それを舞台で使いたい」というものがありました。
このとき何をするか?!
まずはDAWソフトで複数トラックにて別々にかけたイコライザーとコンプなどの編集をミックスし、マスタリングソフトへ。
そこから、全体のイコライザー、リバーブ、コンプレッサー、ピッチ補正、ディレイ、ノイズリダクションとフル装備で編集します。
まさにじゃがりこ飯。
100円のじゃがりこを使ってどこまで1万円コースの高級料理っぽく見せられるか?!が勝負です。
ところが、豊洲で競り落としてきた最高級の本マグロだとどうでしょうか?
熟練の職人が最高級の刺身包丁で切る、そして盛る。
これだけです。
もちろんこの「これだけ」が、超簡単であり、難しい部分でもあります。
現代のマスタリングはこういった背景があるため、当講座の最初の方で紹介した、良いマイクアンプと、良いADCを使い、最高級の本マグロを自分で調達しましょうということなのです。
とっても大事な話
良いマグロはスプーンですくって塩かけて食べるだけでも感動しますよね。
筆者はイコライザーとはこの塩の部分だと思っています。
じゃがりこ飯職人になるわけではない
これまでじゃがりこで高級コース料理を作る方法を検索したりして挫折してきた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「各種プラグインの使い方や、効果効能・・・覚えられないよ。」
「もうこんなに大変だったら外注しよう。。。」
となってしまっているのではないでしょうか。
全くそんな必要はございません。
豊洲で最高級のマグロを目利きし、手に入れればあとは包丁で最高のカットを入れるだけ。
カットの仕方は経験を積めばできるようになります。
覚えるべきたった3つの工程

ノーマライズ
音を数値化して、整えます。
Youtubeなどでは音が極端に小さかったりすることがありますが、これはノーマライズが出来ていないため。
だいたいどのデバイスで視聴しても同じようなボリューム感で聴こえるようにしなければいけません。
これを覚えるだけでもあなたの映像やコンテンツはワンランクアップすること間違いありません。
イコライザー&(ノイズ処理)
EQと呼ばれる処理で、ミキサーにもセットになっているほど、ほぼどんな状況下でも使用します。
実はノイズ処理もこのイコライザーを駆使するとそれで済んでしまうこともあり、それで済んでしまえばそれに越したことはないわけです。
最高級の本マグロはあれやこれやと手を加えれば加えるほど本来の味からは遠くなっていってしまいますよね。
リバーブ(空間演出)
俗に言われるエコーと呼ばれる効果です。
これで空間の体積を表現します。
使い方を間違えると大変なことに。
これら3つのスキルは最高の魚を料理するときに必要なスキルです。
もし、じゃがりこ飯職人になって、ココナラやファイバなどでマスタリングとミックスでいろんな人からいっぱい受注して作業自体を仕事としてやっていきたい!
という方向けではありませんので、この点の趣旨をしっかりご理解ください。
まとめ
(ダビンチリゾルブで録音はできません。)
この作業のみを仕事にしたい(プロになりたい)のであれば、今、そこにある素材をありとあらゆる手を尽くして「なんとかするプロの技」が必要です。
しかし、「良い音響」を目指す場合、制作しているコンテンツのクオリティーをただ純粋にアップしたいのであれば、良い魚を見る目を養うことと、良い包丁の入れ方を覚えること。
【EQ実践編(ノーマライズまで)】DaVinci Resolveでの使い方(サイト内記事)
こちらの記事もいかがですか?
オーディオやマイクロフォンに関する役立つ情報をお届けしています!
音源ごとに使用機材やマイクロフォンを記載していますので是非参考にしてみてください。 金田式DC録音:五島昭彦氏の録音作品リスト コスパ最強!当スタジオではLEWITTのマイクロフォン激推し中です! 【保存版】LEWITTっていいマイクですか? このセット・・・凄いです・・・ 【無指向性の決定版を完全ガイド】”Tascam DR-05X + バイノーラルマイク” 金田式DCアンプは聞いたことのあるオーディオファンは多いでしょう。
こちらは金田式DCマイク。
市販されているものではないので、かなりのオーディオマニア向けですが、興味のある方はご覧ください。 【金田式DCマイク】 ショップス MK2, DPA2006カプセルでテストレポート 位相変換が必須のため、中級者以降向けの記事ですが、おすすめの無指向性マイク! 【コスパ最高】 COUNTRYMAN ( カントリーマン ) / B3 当スタジオ一番人気の記事はこちら! 天才になるには・・・ 実はとても簡単でした。
ポッドキャストや音楽アルバムも是非チェックしてね!