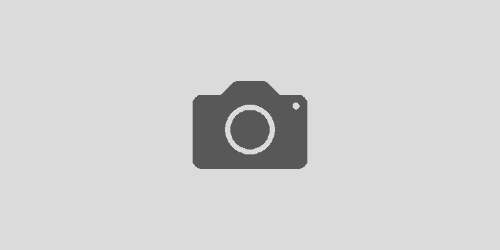マイクセッティングを覚えるためにオーケストラを聴きにいこう

この記事の目次
この記事は広告リンクを含みます。
マイクセッティングというと、偉く難しそうに聞こえますが、簡単にいうとマイクを置く場所です。
- 音源がそこにある。
- 良いマイクを用意する。
- マイクを置く。
- 録音する。
基本的にはこれだけ。
応用編を考えれば環境、残響、音のスピード、湿度、気温などの要因によって位置が変わります。
まずはマイクセッティングとは何か?
そして、いい音を創るためにどれだけ大切な要素なのか?
基礎的な考え方をマスターしてください。

簡易紹介:こうたろう
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
その後金田式DC録音のスタジオに弟子入り
写真・映像スタジオで音響担当を経験し、写真を学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門のピアニスト、またスタジオでは音響エンジニア、フォトグラファーなどマルチメディアクリエーターとして活動中
当記事ではプロのピアニスト、音響エンジニアとしての知識とスキルをシェアしていきます
イコライザーやリバーブ = それ不要です

プラグイン(イコライザーやリバーブなど)というのは、録音した音に含まれている「要素」をより美しくする目的で使用します。
| マイク位置による要素 | 難易度 | |
| イコライザー | 周波数の隙間を考察 | 中 |
| リバーブ | 箱(現場)の大きさ湿度による速度 | 高 |
| ディレイ | 箱(現場)の跳ね返り、マイク同士の距離 | 低 |
と、ざっくりこのように考えることができます。
すべてのプラグイン要素は本来マイクセッティングで演出可能になってきますし、後述しますオーケストラの指揮者はプラグインを使いません。
スタジオワークでプラグインを使う理由
さて、スタジオワークでは後から編集でイコライザーやリバーブ、ディレイなどを駆使して編集していくわけですが、これらは当然生の要素がないために、シュミレーションで付加することになります。
つまり生の要素を足すにこしたことはないけど、残響が○秒のコンサートホールでは収録できないからリバーブを○秒シュミレーションするという具合です。
筆者が昔聞いた話ですが、アナログ時代はスタジオワークでも、生の質感にこだわるアーティストやエンジニアは例えばスネアの音を収録するのに銭湯まで機材を持っていってサンプリングする。
なんてことを当たり前のようにしていたそうです。
【レコードデビュー徹底解説】どこで買う? レコード購入の注意点からおすすめのプレーヤーまで
80年代の終わり頃から90年代にはじめころにはそういったドラムサウンドが流行っていた頃でした。
例えばTears For Fearsなんかは、このあたりの時代を象徴するサウンドと言えるのではないでしょうか。
『プラグインは使うものであり、使い方覚えないと音響はマスターできない。』
という考え方は筆者個人としては否定的です。
これはこれまでも例に出してきた料理で例えると、やはり素材の質が悪ければ悪いほど味付けをしっかりしなければならなくなるというのと同じです。
こちらの『本当は教えたくないピアノ録音のすべて 』でも詳しく解説していますので、是非チェックしてみてください。
音の性質を把握

というわけでプラグインはできるだけ使わずにマイクセッティングを丁寧にするべきである。
というのが当サイトの考え方。
ここで音の性質を簡単に復習しておきましょう。
音は、1秒間に約340m進む・・・
これは有名なお話でご存知の方も多いかと思います。
しかし、音は波形ですので、環境によってその速度は大きく変化するわけです。
例えば湿度が高いと音の速度は遅くなりますし、気温によっても大きく変化します。
1秒間に約340mということですが、これ、結構遅いですよね。
そうなんです。
結構遅いんです。
小学校の頃徒競走でピストルの音が遅れて聞こえてくるのは音の速さが結構遅いから。
ディレイなどを天然で構築する場合はこの速度をつかってはじきの公式でマイクの距離を割り出します。
気温と湿度で大きく左右される
特に湿度。
これは音響環境にとっては最も天敵といえます。
少なくとも湿地帯である日本では西洋楽器の収録は基本的にできないと思っておいた方がいいと思われます。。。
というくらい湿度は大変なのです。
楽器が鳴らなくなるのは当然ですが、音質に関しても張りがなくなり、艶もザラザラ感もなくなります。
この辺りは今後和楽器収録のレクチャー機会がありましたら詳しくみていきたいと思います。
こちらの記事で紹介している龍笛ソロは超ベテランの先生が吹いてくださっていますが、やはり適度な湿度が好ましいとおっしゃっていました。
つまり全ての録音が乾燥すればするほどいいのか?
と言われるとそれは即答できません。
しかし、ナレーションや歌を録音するときに喉を気にして加湿器をかけたり、部屋の湿度をあげておく・・・
なんてことはダメ絶対。
せっかくいい機材を揃えてもその性能を100%発揮しきれません。
環境によって変わる
部屋の環境、壁が木材なのか?
鉄なのか?
それとも吸音材なのか?
それともコンクリートなのか?
部屋に置いてあるモノ、、、例えばデスクなどの素材は何か?
これも音を大きく左右させる要因になります。
いい音を追求するためには収録の際に周囲の環境をチェックして、どんな材質のものがどんな跳ね返り方をするのか?
跳ね返りの速度は?
などなど考慮してセッティングしなければいけません。
ただし、ここは経験によるところが大きいかと思うので習うより慣れろの精神で経験を蓄積していきましょう。
特に都市や人工物で囲まれた環境でのロケ収録などでは、素早く周囲の状況を把握してマイク選び、セッティングをしていくスキルが求められます。
カメラでいうところのライティングと同じ世界観です。
何度も何度も繰り返しテストして体感で覚えていくしかありません。
芸術の世界にHow to や方程式はありませんから、ここが芸術の最も面白い領域にはなりますが。
よく考えられたオーケストラの配置

みなさんはオーケストラのコンサートに行ったことがありますか?
実はオーケストラこそ、天然の音響編集の完成形なのです。
ここにいろんな概念が詰まっています。
トランペット&トロンボーンは最後列
金属製で且つ、楽器自体の菅の長さが短く、客席に向かってダイレクトに音を届けるトランペットとトロンボーンは最後列に位置しています。
これらの直管型の楽器はピンポイントに狙った場所に音を届ける指向性を持っているわけです。
ホルンやチューバは反響前提
一方でホルンやチューバなどの菅が長く、ベルも反響版目掛けて設計されている楽器は音の速度も遅く、反響させて楽器本来の音を作り上げるタイプの楽器はオーケストラ中間部分に位置しています。
弦楽器は上に向かう
バイオリンやビオラなどの弦楽器は基本的に上に向かいます。
チェロやコントラバスは縦に音が流れますが、チェロ奏者などはアンサンブルやオーケストラなど編成や状況に応じて楽器の角度を変えているわけです。
舞台上での音響
コントラバスやチェロが低域を舞台の底支えとして機能し、その上にバイオリンとビオラ群などで軸となる音ばを作り上げる。
そこにトランペットやトロンボーンを注入し混ぜる。
そして反響前提の楽器群で全体を包み込み、コーティングする。
このミックス作業を指揮者は指揮台でやっているわけなんですね。
つまり、ミキシングエンジニアというのは指揮者そのものなわけです。
【音響・舞台運営に必見】ギャラの勘定まで〜現場での業界用語辞典
指揮者はプラグインを使わない
当然ですが、オーケストラの指揮者は客席へ音を届ける前にプラグインなどは使っていません。
プラグインなどは使わずに現場ごとに微妙に音響を調整しながら本番を迎えます。
Aというコンサートホールではこのバランスだったけど、Bというコンサートホールではどうも混ざりが悪い、なのでこの部分のトロンボーンは音の速度を少し落としてください。
本番中でも非常に細かい指示を指揮棒で出します。
この部分の〇〇のパートは少しだけベルの位置を上げたい!というときに、大きめに棒を振り視線を集めます。
そこで音響が変わるわけです。
リハーサルで指示して細かく音響を作り上げ、本番中でも微調整しています。
録音は本来これくらいの緊張感を持って挑むと良い音響が作れるのではないでしょうか。
「指揮者とか俺でもできるんじゃね?!」と思われがちですが・・・ここまで読んできてくださった方にしか伝わらない指揮者の大切な役目の一つが音響と言えます。
機械では調整できない極微細なフェーダーコントロールをしているわけですね!
例え本番中であっても時には無言の圧力でパートのボリュームやアーテュキレーションをコントロールしています。
それはお客さんの数、お客さんが着ている服の材質などでホールの反響が変化するため、リハーサルでは想定できない音響が発生し、本番でコントロールするわけです。
まとめ
- プラグインは使わずにマイクセッティングでイコライザー、リバーブ、ディレイは表現できる。
- できればマイクセッティングだけで表現できればベスト。
- プラグインは補助的に使う。
- 可能なら指揮者の隣でオケを聴いてみる、もしくは指揮をしてみる。
出来ればオーケストラを生で一度聞きに行ってみてください。
その際もできるだけ同じ編成で、同じホールで一番高い席と一番安い席を聞き比べたりしてみましょう。
そしてできればヨーロッパのオーケストラを現地で聞いてみてください。
仮に航空券が10万円かかったとしても、ヨーロッパのオーケストラは日本で聞くチケットの平均して10分の1ほどのお値段で聞くことができます。
価格は10分の1、性能は100倍!?とヨーロッパまでわざわざ聞きに行くことは実はかなりコスパが良いんです!
短期集中で良い耳を育てるために使う投資としては日本で1万円のコンサートに10回行くよりは、ヨーロッパで10ユーロのコンサート10回行った方が耳を鍛えるには遥かに良い投資になります。
地域のイベントの吹奏楽のコンサートなどは無料で参加できるものがありますのでそちらも良い経験値が得られるかもしれません。
その際、どの楽器がどんな方向で、どんな速度で、どんな混ざり方をしているのか?
そして箱(ホールや場所)はどんな特性があるのか?
などに注目しながら脳内の引き出しを増やしていってください。
こちらの記事もいかがですか?
オーディオやマイクロフォンに関する役立つ情報をお届けしています!
こちらは金田式DCマイク。
市販されているものではないので、かなりのオーディオマニア向けですが、興味のある方はご覧ください。 【金田式DCマイク】 ショップス MK2, DPA2006カプセルでテストレポート 位相変換が必須のため、中級者以降向けの記事ですが、おすすめの無指向性マイク! 【コスパ最高】 COUNTRYMAN ( カントリーマン ) / B3 当スタジオ一番人気の記事はこちら! 天才になるには・・・ 実はとても簡単でした。