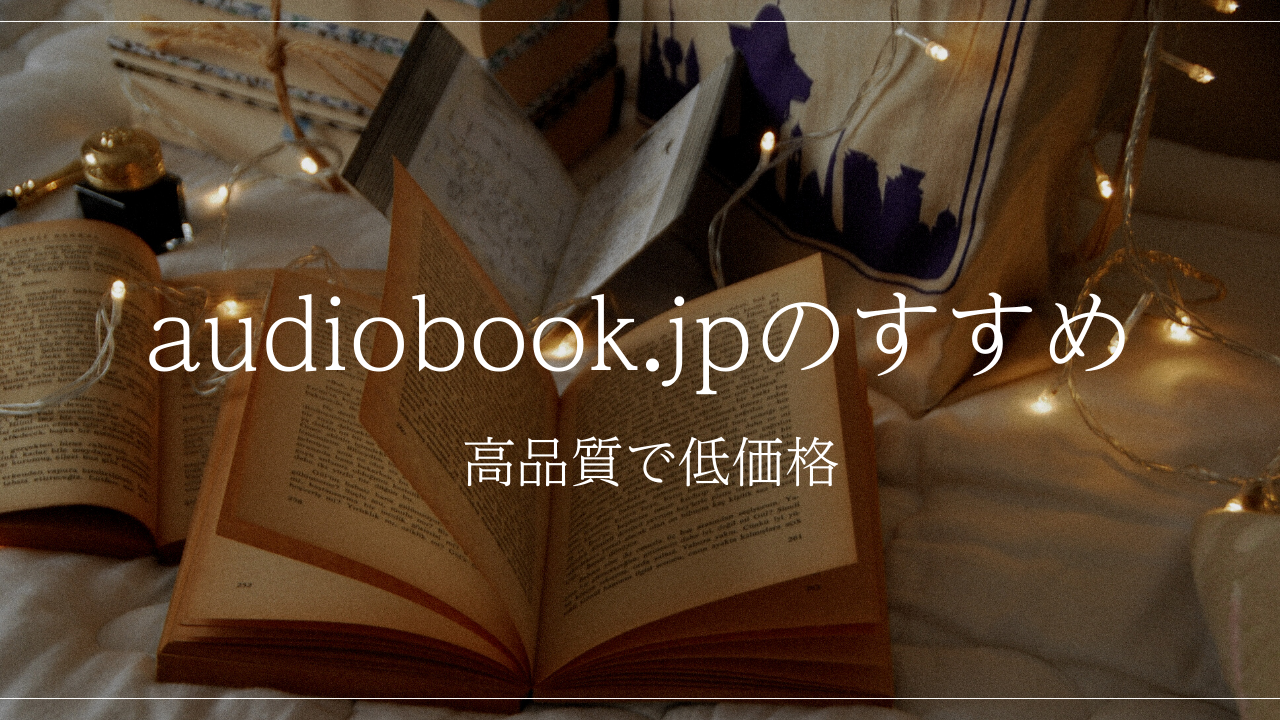吹奏楽部で楽器を買うならプラスチックで決まりな話【チューバ編】

この記事の目次
🚨 緊急のお知らせとお願い 🚨
いつもKotaro Studioをご覧いただき、心より感謝申し上げます。
今回、私たちの活動をさらに広げるため、音楽家人生をかけたクラウドファンディングをスタートしました。
ヒーリング音楽の世界で、より多くの人々に癒しと希望を届けるための挑戦です。皆様のお力添えがあれば、この夢を現実にすることができます。
ご支援をいただける方はもちろん、サイトをシェアしていただくだけでも大きな励みになります。また、応援の声をSNSでシェアしていただければ、私たちの士気も大きく高まります。
短い期間ではありますが、11月30日までに目標を達成し、皆様に素晴らしい音楽をお届けできるよう全力を尽くします。どうか応援をよろしくお願いいたします。

執筆:朝比奈 幸太郎 / 音楽家・宗教文化研究家
音楽大学で民族音楽を研究。
卒業後ピアニストとして活動。
インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。
ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。
ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。
録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。
オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。
現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。
プラスチックの楽器でいいの?と考えてしまう方、多いのではないですか?
いいんでしょうか?
いいんです!
とってもいいんです!
子供が吹奏楽部で楽器を欲しがっているという親御さんも必見の記事。
何より成長期に重たい金属の楽器振り回すのはやめた方がいい。。。
チューバの音源をたまたま発見したのですが、音響のプロの耳で聞いても間違いなくチューバです。
こんな方におすすめ!
- 親に楽器をおねだりしたい方。
- 子供が吹奏楽部で楽器欲しがってる方。
- 野球観戦にいつも重たい金属のラッパ持って行っている方。
- 社会人吹奏楽サークルで楽器再開したい方。
金属の10分の1
まずは最初に驚いてください。
金属の10分の1くらいのお値段です。
PLAYTECH ( プレイテック ) / PTHT-100BK ハイブリッドチューバ ブラック をサウンドハウスで見るとりあえず安く導入できるのはまずは最大のポイント。
金属製のチューバの場合はもちろんピンキリではありますが、下は探せば20万程〜上は300万くらいまでが目安でしょうか。
音大でチューバ専攻になるために購入する楽器がちょうど300〜400万程度です。
吹奏楽部で部活動として楽しむには少々常識はずれのお値段だと言えます。

プラスチックを購入する4つのメリット
次にプラスチックにすることで得られるメリットをピックアップしていきます。
基本的にメリットしかありません。
見ていきましょう。
1、身体への負担軽減
筆者は中学〜大学まで吹奏楽界にどっぷり浸かっており、高校では全国大会常連の強豪校で東京行ったり地方興行にいったり、イベントやテーマパークでの伴奏や演奏をしたりと、ノーギャラで使えるプロみたいな高校生活を送っていました。
どっぷり浸かったからわかるのですが、チューバの重さというのは、特に成長期にダイレクトに差し掛かる中学生活では相当なダメージと負担になります。
昨今だと昔のようなスパルタ部活動もなかなかないかもしれませんが、例えば何かの式典の際など、チューバは床や地面に楽器をおくことは基本的に許されない風潮がありました。
当時はずっと持っていたんですが、相当きつい。
成長期にダイレクトに差し掛かる大事な時期に無駄な体力を重たい金属で奪われないで済みます。
2、お値段が安い
冒頭でもお伝えしましたが、これはかなり大きいです。
チューバくらいの規模の楽器になると基本的に部活動で借りられると思います。
しかし、やっぱり不衛生です。
もう現代では吹奏楽器をシェアするなんてちょっと厳しい人多いと思います。
自分の楽器を購入すると衛生的に活動できるでしょう。
この衛生面は次のメンテナンスにもつながってきます。
トランペットなどの小型楽器だともっとコスパよくなりますね!
3、メンテナンスが楽
これもサウンドハウスさんの公式紹介動画でも言われていますが、メンテナンスが果てしなく楽になります。
金属製の場合はオイルにしても複数種類を使い分けるのは当たり前ですし、チューニング管のグリス、また、ここが最高に大変なのが、金属製の場合は専用の磨き材を使ってボディ全体を磨いてやらないといけない。
錆防止のためもありますし、やはり本番前は見た目の問題もあり専用のポリッシュで磨く人が多いです。
金属製も金管楽器の場合は水で丸洗いができますが、プラスチックの場合はさらに丸洗いのハードルが下がります。
休日にお父さんが洗車でもする時についでに丸洗いすればOK。
4、金属アレルギー対策
大きいのです。
金属アレルギーのため、やりたかった楽器ができなかった・・・なんて方もいらっしゃるかもしれません。
しかもアレルギーってある日突然現れたりしますし、軽微な場合は本人も気が付かずにボディーブローのように効いていて・・・なんてこともあるかもしれません。
プラスチックなら大丈夫。
プラスチックにするたった2つのデメリット
もちろんデメリットの部分もしっかり見ていく必要があります。
1、プロを目指すならきつい
やっていくうちにプロを目指すようになったら金属製を買えばいいじゃないかという話もあるかと思うのですが、その場合でもやっぱりプロを目指すならプラスチックから入るのはちょっとまずいです。
とはいえ、チューバでプロを目指すというのは相当な根気とパワーと忍耐力が必要になりますから、こういったデメリットも吹き飛ばせるかと思います。
もし、最初からチューバ(金管楽器)のプロを目指す、または音高や音大を目指すという方は慎重に検討した方がいいでしょう。
2、まだ社会が受け入れていない
おそらく金属製が最高に決まってる。
という先入観はまだまだ数年、または数十年は消えないでしょう。
特に吹奏楽業界はプロやセミプロ含めてたくさんの人が出入りしている世界で、実に様々な意見や考え方の人が入り乱れています。
社会全体としてプラスチックの楽器を肯定的な視点で見れるようになるには時間がかかると思います。
音楽家から見るプラスチックが最高な理由
ここから先は音楽家としての視点で管楽器をプラスチック化していっていい理由をお届けします。
文化的視点で見た時に、やっぱり本物がいいんじゃないのか。
音楽家なら本物を推奨するべきでは?
といったご意見もあるかと思います。
本物とは何かを考える
さて、ここで本物とは何かという視点で見ていきましょう。
金管楽器の元来の性質、目的は信号でした。
信号ラッパという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、元々はピストンを使って音階を作ることはできず、菅自体の長さだけで音を形成していました。
だんだん持ち物として持つのもめんどくさくなっていきます。
重いですからね。
じゃあ肩にかけられないか?
という発想で生まれたのがホルンという楽器です。
ホルンは当時持ち物としての信号管を肩にかけられる画期的な楽器で、主に郵便配達の到着を知らせる合図のために郵便屋さんが使っていました。
そこからヨーロッパで栄えていった金管楽器の文化。
この文化は守らなくてはいけません。
ここは音楽家として絶対に譲れない意見として記しておきます。
しかし、果たして中学生、高校生が部活動で守らなければいけないことでしょうか?
およそ西洋楽器を演奏するのに全く適していない環境の日本で中高生が守っていかなければいけない文化だとは筆者は思えません。
プロの板前
まな板がすごくいい例えかもしれません。
そりゃ檜のまな板は最高です。
しかし手入れが大変。
プロの板前さんだって場合によってはプラスチックのまな板を使うかもしれません。
しかし回ってないし値札も書いていないお寿司屋さんではやっぱり檜のまな板使ってほしい・・・
そう、文化を守るために。
プロの板前さんはおそらく現在プラスチックのまな板を否定も肯定もしていないでしょう。
プラスチックはダメだとかそういう話じゃないかと思います。
文化を守るのはプロの役目
プロの寿司職人が檜のまな板のお手入れができないとなればそりゃ問題です。
神事を行うのにプラスチックの龍笛ではダメです。
ウィーンフィルがプラスチックの楽器使っちゃダメです。
写真家が自家現像できないとなれば問題です。
そう、文化を守る文化の番人はプロに任せていればいい。
中高生に任せる必要はありません。
おすすめのカラー
好きなカラーを選べるのもおもしろいポイントです。
金属製だと基本的にシルバーかゴールドの二択となります。
サウンドハウスはもちろんですが、Amazonなどでも取り扱いがありますのでまずは一覧でチェックしていきましょう。
白マジックでサイン:ブラック
ブラックモデルはやっぱりかっこいい!
PLAYTECH ( プレイテック ) / PTHT-100BK ハイブリッドチューバ ブラック をサウンドハウスで見る個性的に攻める:パープル
PLAYTECH ( プレイテック ) / PTBB-100PR チューバ プラスチック パープル をサウンドハウスで見るインテリアにも:ブルー
PLAYTECH ( プレイテック ) / PTHT-100BL ハイブリッドチューバ ブルー をサウンドハウスで見る部活動が終わってインテリアとして使いたい時にパープルやレッドの場合は合わせ方が難しいですが、ブルーだと合わせやすいのではないでしょうか。
王道:ゴールド
PLAYTECH ( プレイテック ) / PTBB-100GD チューバ ゴールド プラスチック をサウンドハウスで見るそんな時は王道のゴールドで解決です。
これだとバンド全体のイメージに一切影響を与えることなく、プラスチックの恩恵を手に入れることができます。
ピストン or ロータリー
選択肢としてピストンとロータリーどちらを選べばいいでしょうか?
王道を行くならピストン型ではありますが、プラスチックの場合はロータリー型にしておいた方がいい。
どちらの駆動方法でもこの駆動部分が壊れやすいのは同じですが、ピストンの場合はやはり突起物に衝撃が加わると致命傷となるリスクが高い点が懸念されます。
B管 or C管
ブラックとグリーンだけC管モデルもラインナップされています。
PLAYTECH ( プレイテック ) / チューバ C管 プラスチック ブラック PTCB100BK をサウンドハウスで見てみる日本の吹奏楽界はほとんどの学校でB管を軸に活動しています。
音名などについての初級の楽典は「音楽家育成塾」の記事にて詳しく解説していますので、チェックしてみてね!
フォローも忘れずに!
顧問やコーチに反対される場合
顧問の先生やコーチから反対される場合もあるかもしれません。
現在はさすがに少なくなっていると思いますが、つい20年ほど前までは顧問と楽器業者がつながっていて顧問の先生がキックバックをもらうケースというのは実際に存在していました。
プロのオケ奏者もびっくりの世界一流ブランドの楽器を中学一年生の親御さんに半強制的に買わせていた先生もいます。
多分現代なら大炎上間違いなしです。
まだあまり可視化されていないような部活動ではもしかするとこういう悪しきキックバック文化も残っているかもしれません。
その場合はやっぱりプロが使うような最高級の楽器を買わせた方が顧問の先生は儲かるわけですから、あまりにも強く反対し、自身のすすめる業者を強く押してくる場合(割引が効くから等)ちょっと疑ってもいいかもしれません。
反対される最も大きな理由として挙げてくるのは筆者がデメリットでも上げた、『本物性』だと思います。
その場合は先述の通り、中高生の子どもたちが西洋音楽の歴史と文化を背負う必要があるのかどうかを一度冷静に話し合って考えてみてはいかがでしょうか。
プラスチックの管楽器、最高です。
音楽家を目指す方、音大を目指す方、オーディオが好きな方は是非他の記事も遊びに来てくださいね!