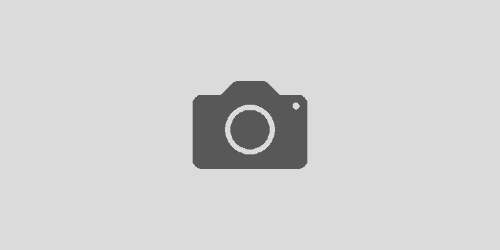【RME】MADI & Dante対応12chリファレンス・マイク・プリアンプ「12Mic-D」発売〜注意点など

RMEは透明感のある音として当スタジオでもフラッグシップ機としていくつかおすすめをシェアしています。

簡易紹介:こうたろう
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
その後金田式DC録音のスタジオに弟子入り
プログラミング(C)を株式会社ジオセンスのCEO小林一英氏よりを学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門のピアニスト、またスタジオでは音響エンジニア、フォトグラファーなどマルチメディアクリエーターとして活動中
当記事ではプログラマー、音響エンジニアとして知識とスキルをシェアしていきます
関連サイト
RME製品は相性の良いマイクロフォンがはっきりしているため、RMEサウンドが合う人はシステムを組みやすいという特徴があります。
ただしハイアマチュアの方やプロの方でも使う人を選ぶ機種でもあります。
まとめの部分にて上級者向けの注意点などもまとめていますので是非最後まで読んでいってください。
12Mic-Dは2023年4月25日に発売。
Danteシステムとは
DanteシステムはAudinate社が開発しました。
これまでバラバラだった送受信のケーブル類をイーサネットケーブルに置き換えることにより、長距離でのノイズ発生リスクなどを極端に抑えることに成功しています。
こちらは初期のプロトタイプ金田式DC録音の100m以上の伝送試験の様子。
特徴など
12Mic入力でハード面もシンプルな構成。
1Uに収まるコンパクト性能にデジタル拡張性が高くADCやDACも内蔵されているので、ドイツらしい非常に合理的な製品。
12Mic入力なので、ワンポイント録音や、ステレオペア録音をベースとする方には少しスペックオーバーかもしれません。
12Mic-Dの用途としては、純粋なレコーディング業務というよりもステージボックスやDanteシステムを駆使したネットワークオーディオインターフェイスとしての立ち位置が強いです。
Danteシステムの恩恵を受けやすいコンサートホールでの音響システムの構築や数百メートル規模のマイクケーブルを混線しなければいけない現場で優位に機能します。
純粋なレコーディング業務で言うと例えばDURecを搭載したFireface UFX IIなどの優れた製品が他にもありますので、用途をしっかりと考察して設備投資しなければいけません。
Fireface UFX II オーディオ・インターフェイス&レコーダーをサウンドハウスでチェック12Mic-Dの機能面でいえば入力1から4チャンネルまでは、TRS入力に対応しており、ハイ・インピーダンスに切り替えられるためバンド収録などもスムーズ且つコンパクトなシステムで収録可能です。
MADI入出力、ADAT出力も備えているため拡張性は問題なし。
ZOOM F3のマイクアンプが非常に優秀で昨今はサウンドデバイスとの差もわからなくなるほどですが、さすがにそこはRME。
F3 Field Recorder / サウンドハウスで見てみるRMEクラスになると一段別のレベルに連れて行ってくれます。
12Mic-Dと相性の良いマイク
RME製品全般に言えることですが、RMEといえばDPAとの相性が抜群であると筆者は感じています。
透明感と透明感の融合。
DPAだと4006(無指向性フラッグシップ)や4011(指向性フラッグシップ)などは最高の組み合わせではないでしょうか。
DPA ( ディーピーエー ) / ST4006A ステレオペア をサウンドハウスで見てみるモニターヘッドホンはもちろんゼンハイザーのHD25。
オーディオの世界でいうとRMEは世界トップクラスの音を提供してくれることは間違いありませんが、マイクを選び、マスターレコーダーも必要になるため、プロオーディオ機器だけに上級者向けの機種になります。
初心者の方は初心者向けカテゴリーで情報を集めてください。
また、ワンポイント録音やステレオペア録音でシンプルに空間を切り取る録音をしたい方はもう少しチャンネル数の少ないものでOK。
音鉄さんのバイブルを作りました!音響のプロが教えるマニア度別音鉄デビューセット!
上級者向けのまとめ:注意点など
マイクアンプとしてリリースされていますが、一般的に言う純粋な単体マイクアンプとしては使えないのかな?
設計上アナログのマイクアンプ部からADCされ、一度デジタル処理されたものをDACで出力されます。
もちろん一般的にはデジタルで送受信しますので何も問題はないですが、例えばオープンリールでのアナログ録音をする方にとっては大きな問題点になります。
加えて当スタジオの音響顧問:五島昭彦氏にも意見をうかがったところ、この懸念点に加え、DSD録音もできないよねと言う見解。
純粋にマイクアンプとして使いたい方は注意してください。
Danteシステムでの管制塔としての役割が非常に強いので、ハイアマチュアの方やオーディオマニアの方、プロエンジニアの方はレコーディング業務にシステムとして機能するのかどうかしっかり考察しましょう。
- アナログ出力周波数特性 @ 44.1 kHz、-0.5 dB:9 Hz ~ 22 kHz
- アナログ出力周波数特性 @ 96 kHz, -0.5 dB:9 Hz ~ 45 kHz
- アナログ出力周波数特性 @ 192 kHz、-1 dB:8 Hz ~ 75 kHz
スペックにもあるように帯域も制限されているのも特徴。
ホールでの管制塔の他にモニタールームと録音ルームが分かれている場合(Kotaro Studioの手法では同じ場所でモニターする)には便利に機能します。
MADIもしくはDanteを使って構築すれば演者もエンジニアも非常に快適にレコーディングが進められます。