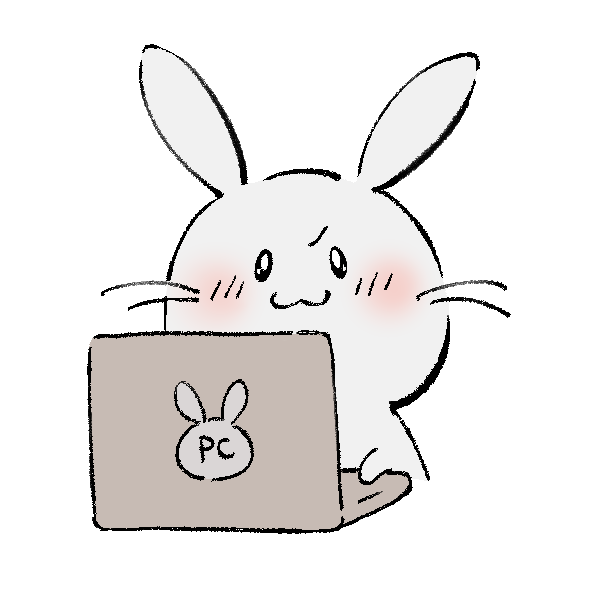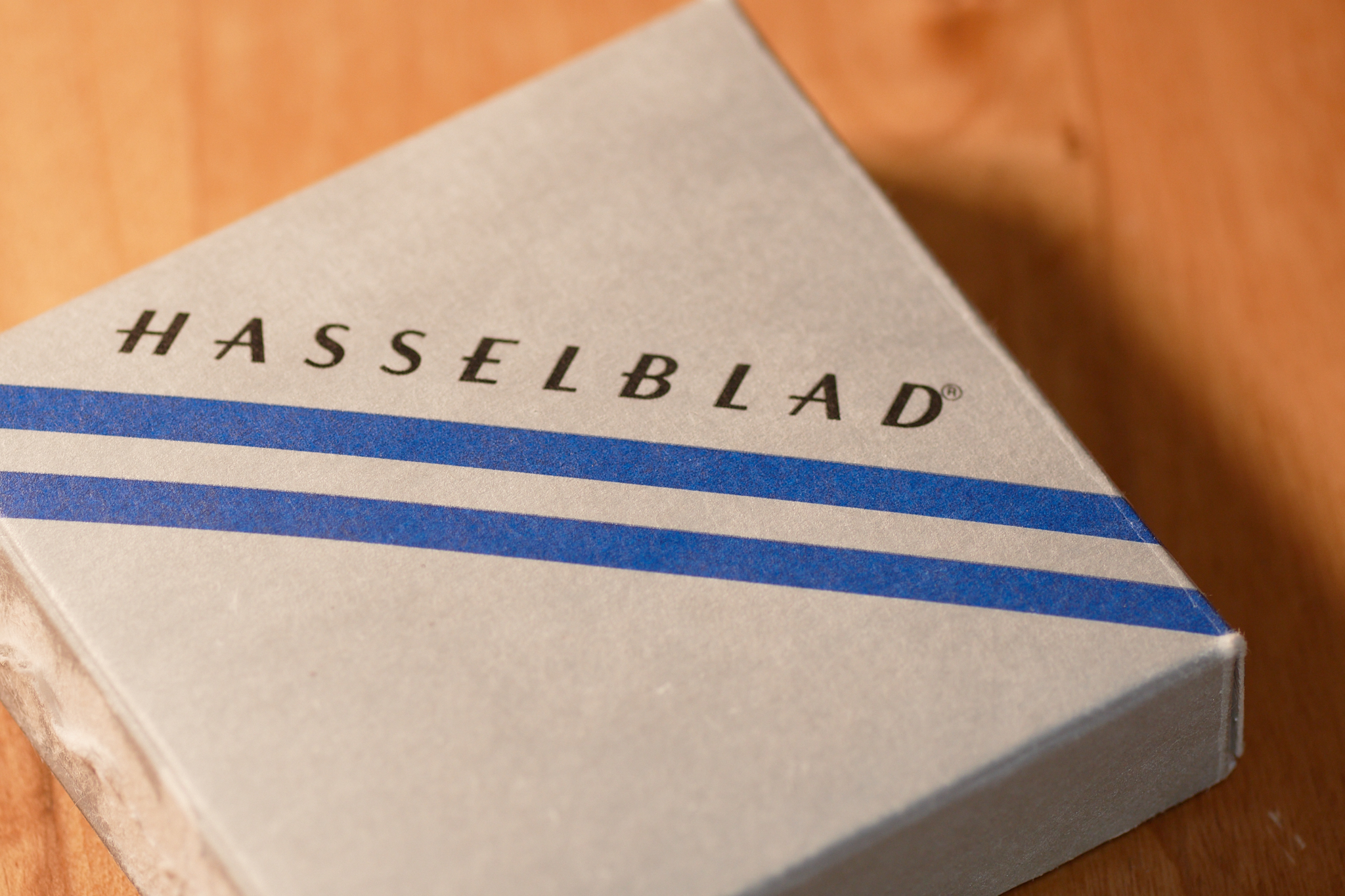バルナック型沈胴式ライカレンズの歴史 / Lecia

この記事の目次
その中でもズミクロンはライカと言えばズミクロンとも言われるほどスタンダード且つライカの代名詞ともなっています。
沈胴タイプのライカレンズはM型ライカが発売されるまで製造されていますので、全種類揃えちゃったという方もいらっしゃるかもしれません。
本日は簡単に沈胴式ライカレンズの歴史について紹介していきます。
バルナック型ライカの歴史を辿る / Oskar Barnack

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家
音楽大学で民族音楽を研究。
卒業後ピアニストとして活動。
インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。
ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。
ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。
録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。
オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。
写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。
現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。
バルナック型沈胴レンズの歴史

1930年:Elmar 50mm F3.5
オールドレンズに少しでも興味を持った方が最初に辿り着く場所がこのElmar 50mm F3.5かもしれません。
それほど有名なバルナック型ライカの元祖沈胴式ライカレンズです。
- 1930年発売
- 総製造数:310000本
- シリアル:なし~760000
- レンズ構成:3群4枚
- 最小絞り:f18、f16、f22
- 最短撮影距離:1m
- フィルター径:36㎜
シリアル番号がないものは市場でも特にレアな存在です。
バルナックA型(Ⅰ型)時代のものであり、最古のバルナックレンズと言っていいでしょう。
コーティングは戦後モデルから。
赤エルマーのフィルム作例は準備中。
1931年:Hektor 50mm f2.5
- 1931年発売
- 総製造本数:9646本
- シリアル:なし〜350000
- レンズ構成:3群6枚
- 最小絞り:f18
- 最短撮影距離:1m
- フィルター径:36mm
- フード:FIKUS(12530)
初期のものにはは無限遠のロックがありませんでした。
製造本数の少なさから中古市場でも見かけることは珍しく、状態のいいものがなかなか手に入りにくいレンズの一つとなっています。
1933年:Summar 50mm F2
Leica Summar 50mm F2(クローム 沈胴)を借りてみる- 1933年
- 総製造本数:122860本 (内2000本は固定鏡胴)
- シリアル:156000-540000
- レンズ構成:4群6枚
- 最小絞り:f18、f12.5
- 最短撮影距離:1m
- フィルター径:36mm
- フード:FIKUS(12530)、SOOMP
発売当初は固定鏡胴だったが、すぐに沈胴式に変更となりました。
沈胴タイプのものは製造本数の多さから比較的安価で手に入りやすいですが、固定鏡胴は2000本しか造られていないため、中古市場では特にプレミア価格がついており、貴重な存在となっています。
1939年:Summitar 50mm F2
- 1939年発売
- 総製造本数:170761本
- シリアル:488000-1236000
- レンズ構成:3群6枚
- 最小絞り:f12.5、f16
- 最短撮影距離:1m
- フィルター径:36mm
- フード:SOOPD
ズマールの後続レンズです。
絞りはシリアルNo.611000まではf12.5。
その後からはf16まで絞れるようになります。
絞りも形も2種類あり、角形ものが6枚羽の丸形になった。
中古市場ではかなりのレアの存在としては、ズミクロンの試作としてレンズ構成がズミクロンで、鏡胴はズミタールのままのものがあり、名前はSummitar*と刻印してあり、高値で取引されます。
1945年:Wollensak Velostigmat 50mm F3.5
- 1945年
- 製造本数:不明
- シリアル:不明
- レンズ構成:3群4枚
- 最小絞り:f16
- 最短撮影距離:1m
- フィルター径:36㎜
ウォーレンサック社のベロスチグマットと読みます。
アメリカのレンズメーカーであるウォーレンサック社に作らせたレンズで、当時のバルナックⅡ型用として販売されていました。
アメリカの会社に外注となったのは、第二次世界大戦、ドイツの敗戦により、ドイツ国内での製造が追いつかなかったという経緯があると言われています。
そのため、新作レンズというよりは、エルマーのコピーレンズと言われています。
1953年:Summicron 50mm F2

Hasselblad Makro-Planar CF 120mm F4 T* レビュー
筆者がバルナック型ライカで最初に選んだレンズがズミクロンでした。
- 1953年発売
- 製造本数:60680本
- シリアル:920000-1750000
- レンズ構成:6群7枚
- 最小絞り:f16
- 最短撮影距離:1m
- フィルター径:39mm
- フード:ITOOY(1580)、IROOA(12571)またはSOOPD、SOOFM
ズミタールの後続レンズとして登場したのがズミクロンF2.0。
1953年からバルナック型ライカからM型ライカへと移行していきました。
最終的にバルナック型ライカはⅢgまで発売されています。(1956年~1960年に製造され、最終型となりました。)
ライカと言えばズミクロンと言うほどのベストセラーモデルとなり、「空気レンズ」を採用しました。
シリアル番号92万台はトリウムの経年変化のためレンズが黄色くなっています。
M型ライカ用の固定鏡胴ズミクロンも約1160本Lスクリューマウントで発売されていますが、数も限られているため見つけるのは非常に困難な上、高値で取引されています。
沈胴式ライカレンズの完成系とも言えるズミクロン。
沈胴式ライカレンズの中でも比較的新しいタイプですので、状態が良いものを見つけやすいモデルとも言えます。
写真や映像用の機器、レンズ類はまずはレンタルで試してみるのがおすすめ!
GOOPASSはわかりやすいシステムで定額でラインナップも豊富でおすすめです!
また、購入の場合は使用後に買い取り可能なマップカメラが個人的には好きです。
グーパスのシステム、使い方や、問題点などはこちらの記事で詳しく紹介しているので是非チェックしてね!
GooPass(グーパス)の評判は?問題点などのデメリットを含めて詳しく解説!カメラのサブスク月額制入れ替え放題サービス
Summicron 50mm F2リリースの年の世界
さて、ズミクロンもう少し深く掘り下げてみたいと思います。
Summicron 50mm F2がリリースされた1953年はどんな世界だったのでしょうか。
気になるニュースをピックアップしてみました。
- 2月1日 : NHKが日本で初のテレビジョン本放送を東京で開始。
- 3月5日 : ソ連の指導者・スターリンが死去
- 4月 : 永谷園(当時:永谷園本舗)設立
- 4月 : 大塚製薬工場、「オロナインH軟膏」(当時:オロナイン軟膏)発売。
- 10月1日 : 米韓相互防衛条約調印。
- 12月1日 : 板垣退助像の百円紙幣(日本銀行券B百円券)発行開始。
- 12月25日 : 奄美群島が日本に返還。
この年、各地のテレビ局が開局し、全国的に放送が始まりました。
オロナインH軟膏は今でも現役で愛され続けていますよね。
こちらの記事もいかがですか?
カメラや映像に関する情報をまとめています!
Hasselblad (ハッセルブラッド)の歴史を徹底解説!
カメラ機材のレンタルといえばGooPassは有名ですが、メリットと合わせてデメリットや注意点などもしっかり解説!GooPass(グーパス)の評判は?問題点などのデメリットを含めて詳しく解説!カメラのサブスク月額制入れ替え放題サービス
レンズの王様カールツァイスを狙うならコンタックス時代のレンズが比較的安くておすすめ!写りは間違いなくカールツァイスです。
【フィルム作例】Carl Zeiss Planar T* 85mm F1.4 AEG
フィルム写真やりたいけど・・・現像とデータ化は大きな障壁となります。そんなときはこちらの記事で一発解決!
【注意点あり】ネットでフィルム現像 データ化までおすすめの郵送ショップ2選
Kotaro Studioのギャラリーやインスタもフォローしてね!