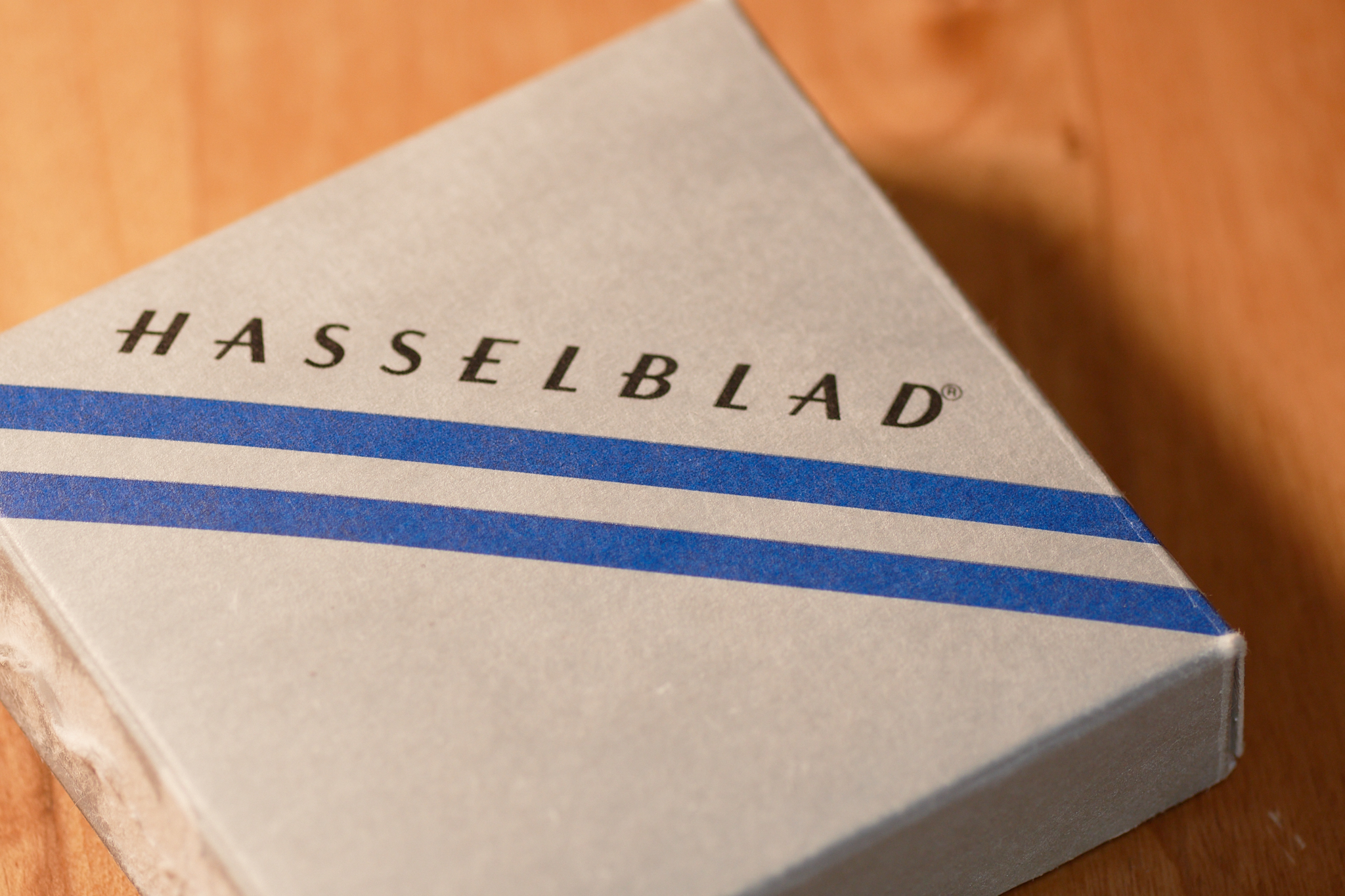【作例&レビュー】Hasselblad Makro-Planar CF 120mm F4 T*

- コスパ
- 6.0
- シャープネス
- 10.0
- 携帯性
- 6.0
- リセール
- 9.0
- 所有感
- 10.0
35mm換算だとだいたい65mmほどの距離感になります。
この記事だけでOK!ハッセルブラッドの使い方や注意点などざっくりまとめ
Hasselblad (ハッセルブラッド)の歴史を徹底解説!

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家
音楽大学で民族音楽を研究。
卒業後ピアニストとして活動。
インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。
ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。
ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。
録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。
オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。
写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。
現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。
1992年製

筆者が購入したのは1992年製のマクロプラナー。
製造年はシリアルナンバーを打ち込むとすぐにわかるデーターベースがあります。
基本的にハッセルブラッドというとやはりPlanar 80mmがベースになるかと思います。
これは35mm換算で50mm相当となり、やはり50mmに始まり、50mmに終わるカメラの世界での標準焦点距離と言えます。
筆者はあえてPlanar 80mmは選択せず、このマクロプラナーと50mmディスタゴンの2本を選びました。
Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical レビュー
コントラストは低め
コントラストは若干低めで雰囲気重視のレンズであると言えます。
ただし、Makro-Planar CF 120mm F4 T*とa6500を使ってのデジタルでは、やはりすごい解像度を見せてくれています。
α6500 ILCE-6500 ボディを借りる
作例


ハッセルブラッドで撮影するライカ・・・なんか夢見心地な時間です。

なんかエモい。
Ektarの雰囲気がいい感じでエモさを演出してくれます。
麦茶ですが、水分の質感はたまりませんよね。

ポジフィルムでの撮影。

Ektar100。
遊具の色味が独特の昭和カラー。
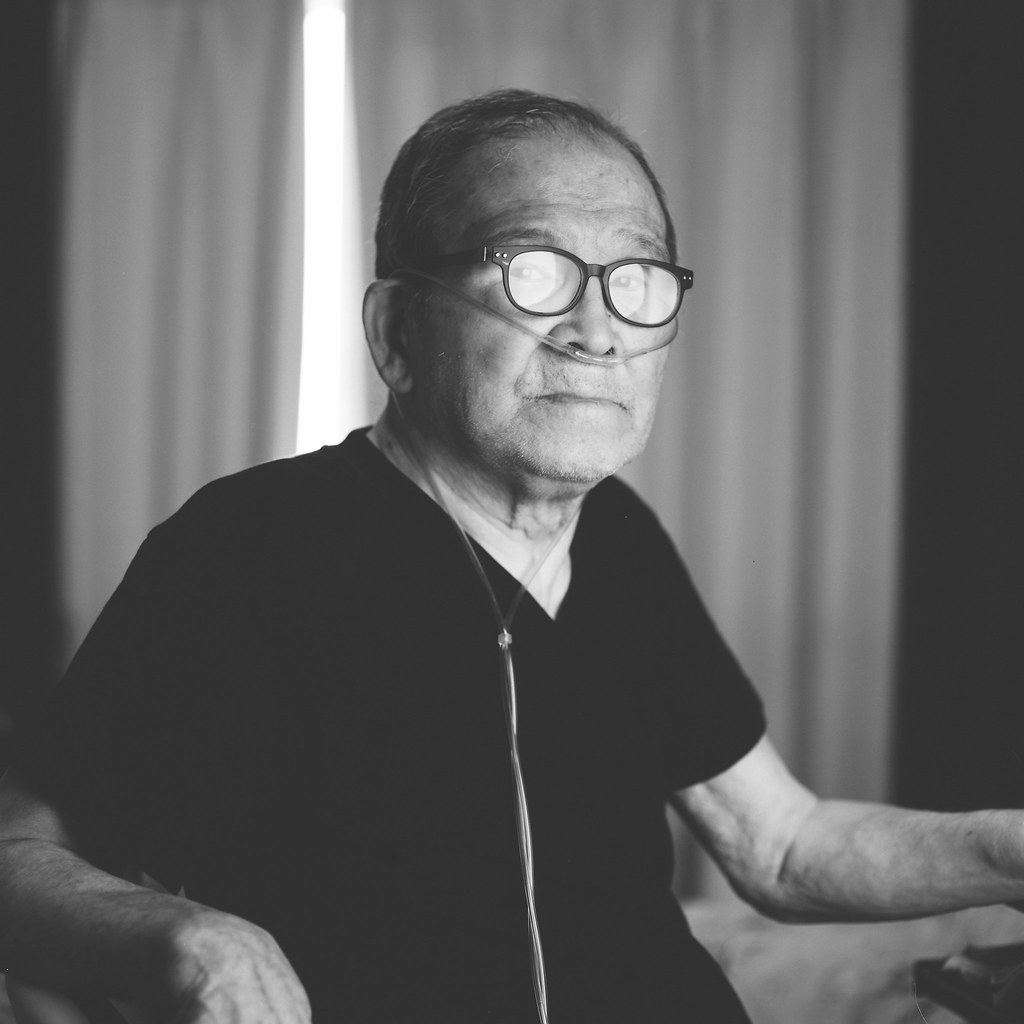
ポートレートの撮影機会がなかなかないので在宅介護中の祖父をACROS IIで撮影。
中判フィルムの風格があります。