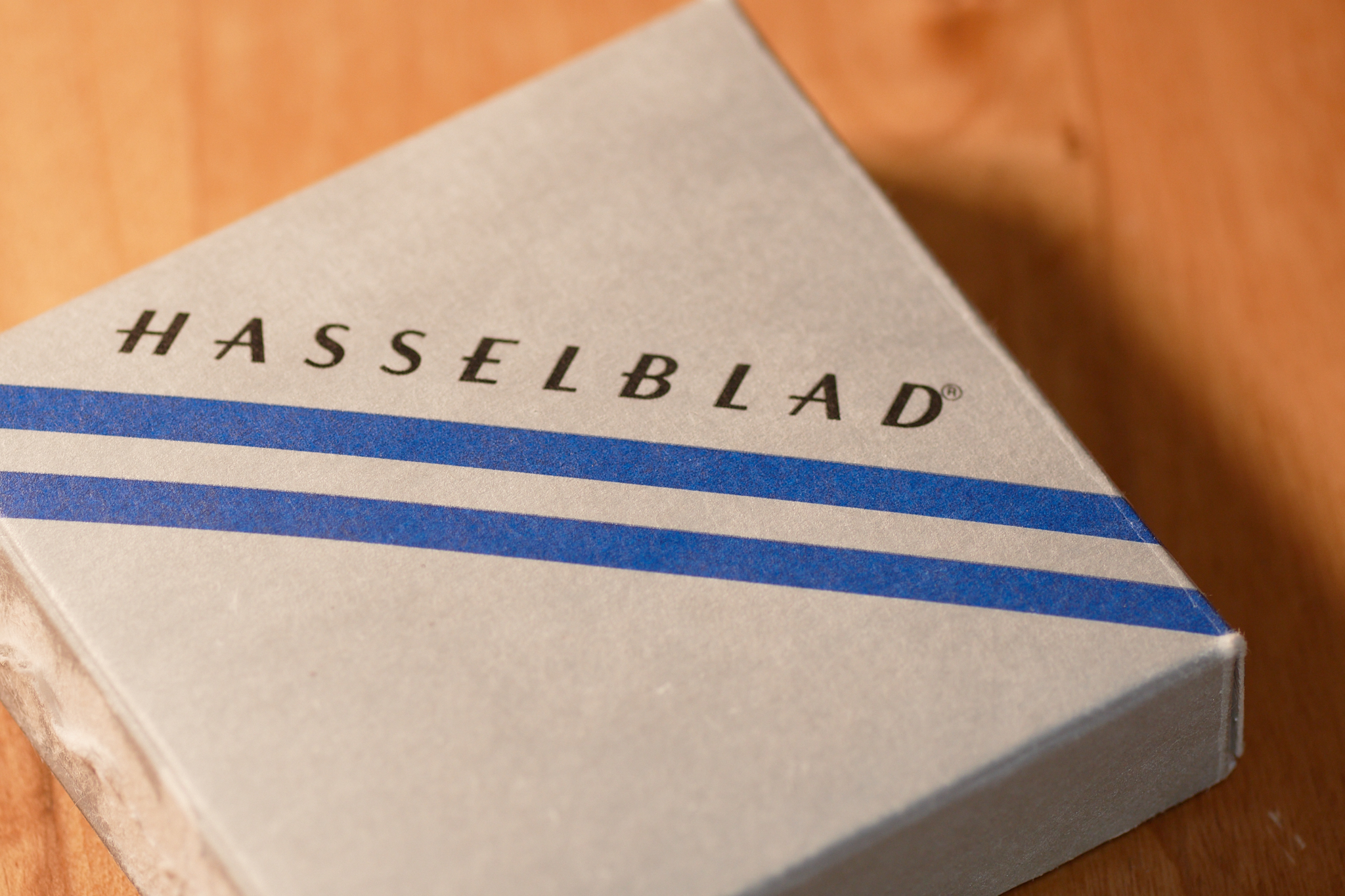【フィルム作例】Hasselblad Carl Zeiss Distagon T* 50mm F/4

6×6の広角写真というと、難しそうですが、はまれば創造性はかなり高まるのではないでしょうか。

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家
音楽大学で民族音楽を研究。
卒業後ピアニストとして活動。
インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。
ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。
ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。
録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。
オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。
写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。
現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。
1982年製

今は亡き西ドイツの刻印がおしゃれ。
Hasselblad関連のシリアル番号から製造年の検索はこちら。
このCarl Zeiss Distagon T* 50mm F/4の画角は35mm換算だと、28mm相当になるわけで、一般的な標準広角の画角になります。
Hasselbladというと、プラナーやマクロプラナーなどの中望遠のイメージがありますが、広角レンズもラインナップされています。
ここからさらに40mmという広角も発売されています。
ただやはり構造上どうしても巨大化、重量化は避けられない点であり、かなり重いです。
さらに絞りの影響がかなりシビアに出ますので、絞り値を慎重に計算していく必要があります。
このディスタゴンは、エルハルト・グラッツェル博士が開発しました。
月面で使われたハッセルブラッドもディスタゴン(60mm)です。
Erhard Glatzel博士
カール・ツァイスのレンズ設計者です。
1925年-2002年(77歳没)ウェストハーレン州マール生まれ。
コンピュータを用いたレンズ設計方法である「グラッツェル法」を確立。
ホロゴンやディスタゴンを発明しました。
ヤシカと提携後のコンタックスRTS用レンズを多く設計したことでも知られています。
1969年7月20日アメリカ航空宇宙局より”The Apollo Achievement Award”を与えられています。
さすがのツァイスと言わせてくれる逸品

その解像感はさすがカールツァイス。
凄まじい描写力です。
フィルム写真作例

2022年春。
近くの公園にて撮影。

Hasselbladというと、やはりプラナーのイメージが強いですが、こういう写真はディスタゴンじゃないと撮れません。

景色を狙っていてランニング中のおじさんが通りかかったのでついでにパシャリ。
ある日のデスク。

フィルム感満載です。
こうやってみるとディスタゴンのこってり具合がよくわかりますよね。
おまけ
ちなみに製造年1982年のドイツの雰囲気はこんな感じ。
YoutubeにてVHSの映像資料が残っていたのでシェアさせていただきます。
Kotaro Studioの癒しの音楽シリーズ432hzピアノ企画を是非体験してみてね!
こちらで紹介しているピアノ音源は全曲癒しの周波数と呼ばれる432hzでチューニングされた作品です。
ニュージーランドやアジア地域で何度もチャートインしています!
2、もののけ姫(もののけ姫より)
3、人生のメリーゴーランド(ハウルの動く城)
4、風の通り道(となりのトトロより)
5、となりのトトロテーマ(となりのトトロより)
6、鳥の人(風の谷のナウシカより)
7、いのちの名前(千と千尋の神隠しより)
8、6番目の駅(千と千尋の神隠しより)
9、ふたたび(千と千尋の神隠しより)
10、いつも何度でも(千と千尋の神隠しより)
11、海の見える街(魔女の宅急便より)
12、晴れた日に…(魔女の宅急便より)
13、やさしさに包まれたなら(魔女の宅急便より)
14、旅立ち(魔女の宅急便より)
15、帰らざる日々(紅の豚より)
16、時には昔の話を(紅の豚より)
17、節子と清太(火垂るの墓より)
18、海のおかあさん(崖の上のポニョより)
19、カントリーロード(耳をすませばより)
20、空から降ってきた少女(魔女の宅急便より)
2、ドライフラワー(優里)
3、ハッピーエンド(映画「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」主題歌)
4、ANSWER(槇原敬之)
5、雪の華(中島美嘉)
6、Everything(ドラマ「やまとなでしこ」主題歌)
7、しるし(社会派ドラマ「14才の母」主題歌)
8、エイリアンズ(キリンジ)
9、First Love(TBS系テレビドラマ『魔女の条件』主題歌)
10、ハナミズキ
11、ひまわりの約束(アニメ映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌)
12、楓(スピッツ) 13、ロビンソン
14、SAY YES(フジテレビ系月9ドラマ「101回目のプロポーズ」主題歌)
15、オールドファッション(ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』主題歌)
16、星の奏でる歌(TVアニメ「シュタインズ・ゲート ゼロ」)
17、炎(映画『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』主題歌)
18、虹(東宝系映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌)
19、366日(映画&ドラマ『赤い糸』の主題歌)
2 小公女セーラ「花のささやき」
3 レ・ミゼラブル 少女コゼット「ma maman」
4 若草物語ナンとジョー先生「明日もお天気」
5 アルプスの少女ハイジ「おしえて」
6 赤毛のアン「きこえるかしら」
7 南の虹のルーシー「虹になりたい」
8 トム・ソーヤの冒険「誰よりも遠くへ」
9 母をたずねて三千里「草原のマルコ」
10 名犬ラッシー「終わらない物語」
11 フランダースの犬 「よあけのみち」
12 ペリーヌ物語「ペリーヌものがたり」