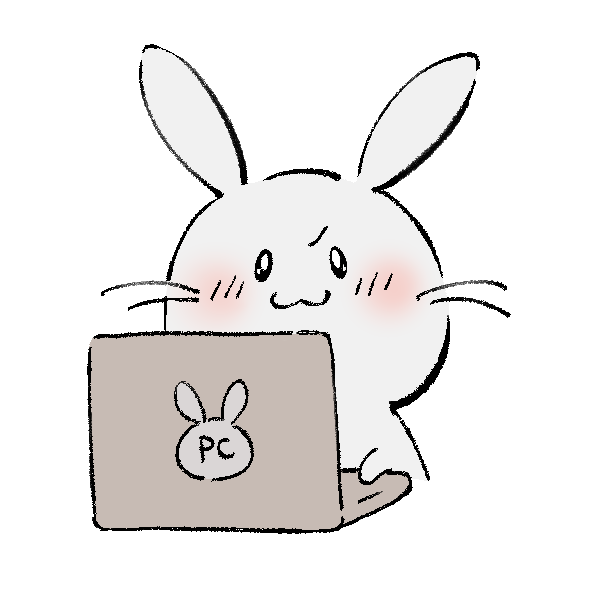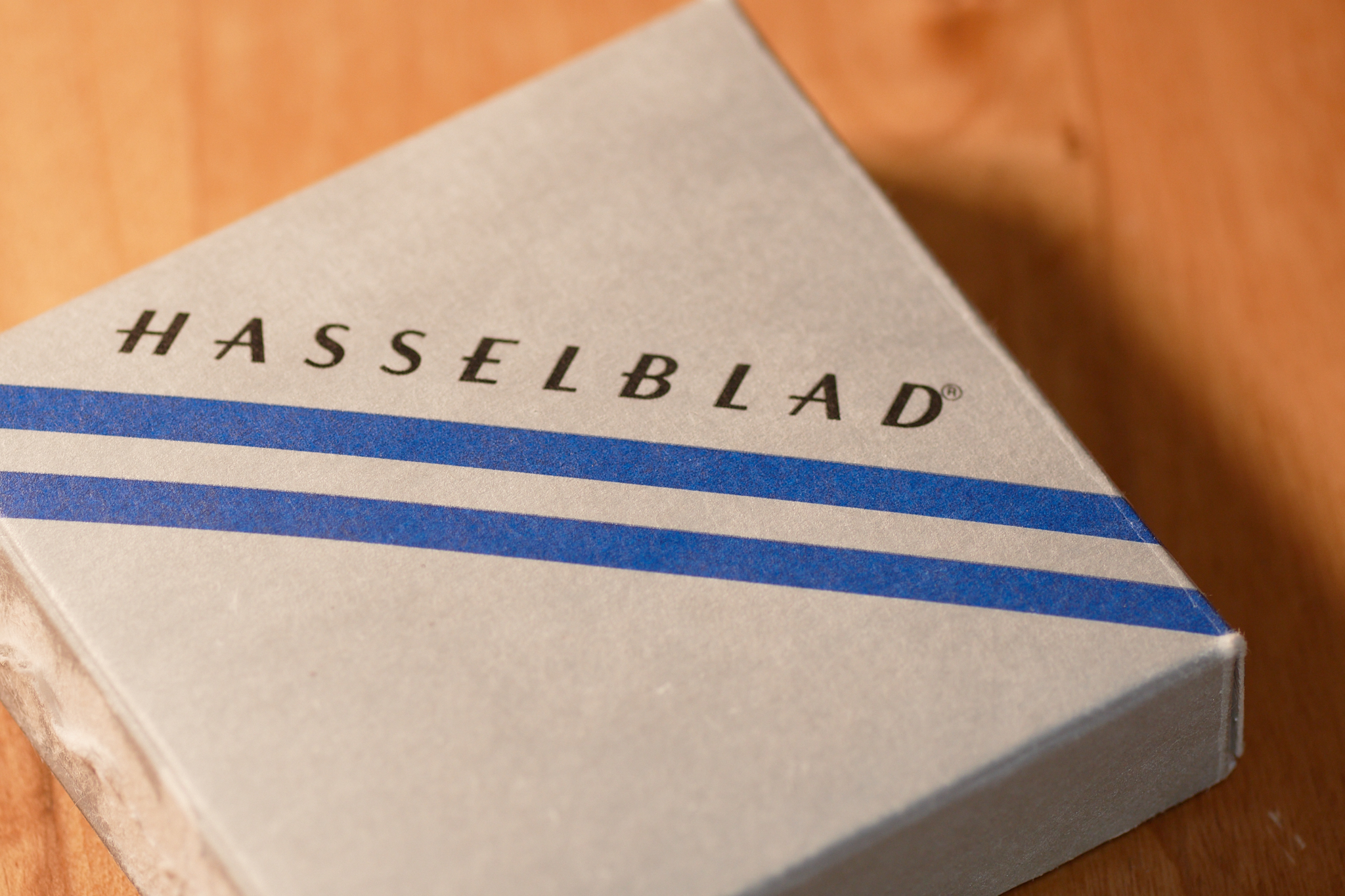【Canon P 作例】国産レンジファインダーの最終型?!

以降の日本はレフ機へと移行していくため、完全機械式のCanon Pは個人的には国産レンジファインダーの最終型と思っています。
フィルムの郵送現像とデータ化に関してはこちらの記事を参考にしてみてくださいね!

執筆:こうたろう / 音楽家・宗教文化研究家
音楽大学で民族音楽を研究。
卒業後ピアニストとして活動。
インプロビゼーション哲学の研究のため北欧スウェーデンへ。
ドイツにて民族音楽研究家のAchim Tangと共同作品を制作リリース。
ドイツでStephan Schneider、日本で金田式DC録音の五島昭彦氏から音響学を学ぶ。
録音エンジニアとして独立し、芸術工房Pinocoaを結成。
オーストリア、アルゼンチンなど国内外の様々なアーティストをプロデュース。
写真家:村上宏治氏の映像チームで映像編集&音響を担当。
現在はヒーリング音響を研究するCuranz Soundsを立ち上げ、世界中に愛と調和の周波数を発信中。
さっそく作例

全部自然光だけで撮影しています。
この日は当スタジオのオーディオコンテンツ、ポッドキャストの収録日で録音エンジニアの五島昭彦氏を迎えての収録でした。

打ち上げで飲むお酒。
高級ジンにはまっていた時期で五島先生にヘンドリクスを用意。
なんできゅうりかっていうと、ヘンドリクスで作るジントニックは最後にきゅうりを浮かべることでヘンドリクスジントニックになります。
きゅうりの驚くべきポテンシャルを体験できますよ!是非お試しあれ!

打ち上げのつまみにつかったマヨネーズ。
夕陽が差し込んでいます。
すべて自然光の露出計もついていないためカンで撮影していますが、ばっちりはまってました。

ハイネケン開けてるってことはもう日も落ちている頃。

ポッドキャストの収録にはZOOM F6を使っていました。
飲み物なんかと一緒に机に置いているので念の為新聞紙を敷いています。
ちなみに同じ日にLeica Ⅲfと赤エルマーで撮影した五島先生がこちら。

【赤エルマー作例】Elmar 50mm f3.5 (L) Red Scale
【完全ガイド】バルナックライカで始まりバルナックライカで終わる〜フィルムカメラの旅完結
3つの特徴と選び方
特徴と中古で購入する際の選び方などを見ていきましょう。
等倍ファインダー
Canon Pの場合はポイントとしてファインダーが等倍ということが挙げられます。
L39マウントなのでLeica Ⅲfと比較したくなりますが、Leica で例えるとM3あたりでしょうか。
M3の形態でL39マウントというニュアンス。
巻き上げレバー
こちらもL39カメラとしてのLeica Ⅲfと比較すると本当に楽になりました。
きっと1960年代にブログがあったらこんな感じで書いてるんでしょう。
一軸不回転シャッター
これが結構ポイント高くて、低速から高速まで回転軸を切り替えることなく調整することができます。
巻き上げレバーとこの一軸不回転シャッターの組み合わせで撮影はとんとん進みます。
中古の選び方
シャッター速度が全速動くかどうかなど基本的なことはしっかりチェックしましょう。
- シャッター速度。
- 巻き上げ。
- 巻き戻しクランプ(フィルムを巻き戻す)
- 全体的なダメージ。
中古ではどのカメラもですが、やはり背面を重視してください。

ここを見れば歴代のオーナーがどんな使い方をしていたかだいたい想像できます。
ここが傷だらけの場合はいろいろと不安が残るので避けた方がいいでしょう。
他にはシャッター幕。
ステンレスの薄膜製が採用されており、Leica Ⅲfのような布製シャッターよりも耐久性が高く、レンズキャップを忘れて放置するとシャッター幕が焦げたり燃えたりするといったこともありません。
さらに布製よりも湿気に強いのが特徴。
さすが湿気大国日本が産んだレンジファインダーです。
一方ではこのようにシワが寄りやすいとも言えます。
ほとんどの個体でこのように若干シワが寄っていますが、これは綺麗なものを見つけるのはかなり根気良く探さないと難しいので仕方ないと割り切りましょう。
もちろん撮影には影響ありません。

ちなみにレンズは、お店で購入する場合は裏側から強い光を当ててみてチェックしてください。
一見綺麗に見えても浮き上がってくる埃や、チリ、傷等がはっきり見えるようになります。
もちろんある程度は仕方ないので、自分の許容範囲内かどうかしっかり確かめてください。


ちなみに個人的な考え方ですが、オールドレンズでこの程度なら最高クオリティーであると考えます。
お店で見る場合はファインダーも同様にチェックするといいですね!

使い方
フィルムの入れ方
ポイントはどのカメラでも同じですが、ギアにしっかりとフィルムの穴を噛ませること。
動画では期限切れフィルムなので分かりやすく何度かやっていますが、こんなに巻いちゃうともったいないので注意してください。
一回くらいはギアにしっかり噛ませられているかチェックしていざ撮影といきましょう!
フィルムの取り出し方
こちらの記事もいかがですか?
カメラや映像に関する情報をまとめています!
Hasselblad (ハッセルブラッド)の歴史を徹底解説!
カメラ機材のレンタルといえばGooPassは有名ですが、メリットと合わせてデメリットや注意点などもしっかり解説!GooPass(グーパス)の評判は?問題点などのデメリットを含めて詳しく解説!カメラのサブスク月額制入れ替え放題サービス
レンズの王様カールツァイスを狙うならコンタックス時代のレンズが比較的安くておすすめ!写りは間違いなくカールツァイスです。
【フィルム作例】Carl Zeiss Planar T* 85mm F1.4 AEG
フィルム写真やりたいけど・・・現像とデータ化は大きな障壁となります。そんなときはこちらの記事で一発解決!
【注意点あり】ネットでフィルム現像 データ化までおすすめの郵送ショップ2選
Kotaro Studioのインスタもフォローしてね!