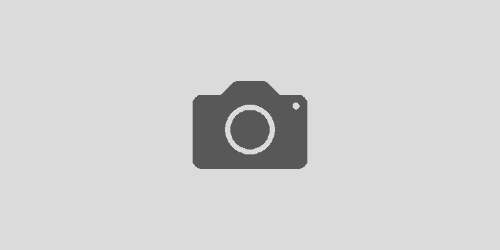ライブで使うマイクの種類を徹底解説|音を支えるプロの選び方

この記事の目次
ライブで使うおしゃれなボーカルマイク?
もしかしてこんなの探してましたか?

後ほどコンデンサーマイクの解説の部分でおしゃれマイクの解説もしていきますね!
ライブ会場で使用されるマイクには、大きく分けて2つの目的があります。
ひとつは「PA(拡声)」のためのマイク。
もうひとつは「録音(収録)」のためのマイクです。
前者は観客に音を“届ける”ためのもの、後者はその音空間を“残す”ためのもの。
この違いを理解すると、あなたのライブの音作りが劇的に変わります。
また、それはアコースティックライブやコンサートでの演者のMCのマイクも含まれます。
この記事ではライブやコンサートで使うマイク、録音よう、PA(MC用マイク)を含めてプロの音響エンジニアが徹底解説していきます。

この記事を担当:朝比奈幸太郎
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイク技術を学び帰国
帰国後、金田式DC録音専門レーベル”タイムマシンレコード”て音響を学ぶ
独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース
その後写真・映像スタジオで音響担当を経験、写真を学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、音楽家, 音響エンジニア,として活動
五島昭彦氏より金田式DC録音の技術を承継中
当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。
♪この記事には広告リンクを含みます♪

【さらなる専門家の監修】録音エンジニア:五島昭彦
学生時代に金田明彦氏に弟子入り。
ワンポイント録音の魅力に取り憑かれ、Panasonic半導体部門を経て、退職後金田式DC録音の専門スタジオ:タイムマシンレコードを設立。
ジャズは北欧系アーティストを中心に様々な美しい旋律を録音。
クラシック関係は国内外の様々なアーティストのレコーディングを担当しており、民族音楽にも精通。
現在は金田式DC録音のDSDレコーディングを中心にアコースティック楽器の収録を軸に活動中。
世界で唯一、金田明彦氏直系の弟子であり、金田明彦氏自らが手がけた金田式DC録音システムを使用している。
🎙️ ライブで使うマイクの基本種類
ライブで使用されるマイクには主に以下の3種類があります。
1. ダイナミックマイク
ライブ現場で最も多く使われているタイプです。
おそらく目にする人も多いでしょう。
- 特徴:頑丈でハウリングに強く、高音圧にも耐える
- メリット:扱いやすく壊れにくい
- デメリット:繊細な音の再現性はやや劣る
代表機種:Shure SM58、Sennheiser e835
→ ほとんどのボーカリストが使用する“定番中の定番”です。
SM58はまさに伝説的な名機で、音楽に携わったことがある方なら必ず聞いたことがあるマイク。
ダイナミックマイクで音がいいので、実際作品のレコーディングにも積極的に使用されます。
ど定番
Shure SM58は1966年に発売されたダイナミックマイクで、SM57の翌年に登場しました。
堅牢な構造と明瞭な中域特性でライブ用ボーカルマイクの定番となり、世界中のアーティストに愛用されています。
現在も基本設計を保ちながら改良が続けられています。
ダイナミックマイクを購入するのにとりあえず58買っておけば失敗と感じることはまずないでしょう。
ダイナミックマイクの基準値といってもいいくらいですので。
最近だと映像制作の一部としてのライブパフォーマンスや、よりルックスや時代劇コスプレなんかのコンテンツも流行っていますので、ビンテージ感のあるアイテムがはまることもあります。
冒頭で紹介したSHURE ( シュア ) / 55SH Series IIも外観がおしゃれで58と同じような音が出せます。
ライブではボーカリスト、MCが使います。
また、ボーカルパフォーマンスをしない、本当にMCだけに使うMC用マイクを探しているという方はクラシックプロ(サウンドハウスのブランド)のダイナミックマイクが激安なのに、めっちゃ使えます。
予算がかなり限定されている場合で、MCにしか使用しない場合は、こちら。
CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CM5 ダイナミックマイクやはりハウリングに強いというのが一つですが、通電していないため、思わぬトラブルを防げるという利点も挙げられます。
スイッチ付きか?スイッチなしか?
ダイナミックマイクの中では、スイッチ付きとスイッチ無しを選べます。
ダイナミックマイクの構造自体は非常にシンプルなので基本的に壊れるということを知りません。
ただ、スイッチという駆動部分はどうしても劣化しやすい部分ですし物理接点を触っているわけですからスイッチ付きを購入した場合はスイッチから壊れていくという形になります。
そのため、購入はできるだけスイッチ無しのものがおすすめ!
ダイナミックマイクはたとえ落としても、ヘッドの部分が凹んでもへっちゃらです。
筆者は発売初期のオール金属のSM58をいまだに持っていますが、バリバリ現役です。
2. コンデンサーマイク
スタジオ用途のイメージが強いですが、近年はライブでも増えています。
- 特徴:広い周波数特性・高感度・繊細な表現力
- メリット:声や楽器の細やかなニュアンスを拾える
- デメリット:電源(ファンタム48V)が必要・ハンドリングノイズに弱い
代表機種:Audio-Technica AE5400、Neumann KMS105
PAを必要最小限に使った静かなホールやアコースティックライブに最適です。
ライブでコンデンサーマイク?!おすすめのコンデンサーハンドマイク5選3. ワイヤレスマイク
ステージでの自由なパフォーマンスには欠かせない存在。
- 特徴:ケーブルがないため、動きやすい
- メリット:ステージ上での取り回しが楽
- デメリット:電池切れ・電波干渉・遅延リスクあり
代表機種:Shure ULXD、Sennheiser EW-D
プロの大規模ライブで主流となっています。
アイドルがヘッドセット型で口元に小さなマイクをつけていたりすることがあるかと思いますが、ヘッドセットタイプでも近年はワイヤレスが主流ですし、ワイヤレスじゃないマイクでもワイヤレス化するのはそう難しくありません。
手持ちのダイナミックマイクやモニターをワイヤレス化する方法🎤 ライブでの用途別おすすめマイク選びを徹底解説
ライブパフォーマンスの音質を決定づける最も重要な要素のひとつが「マイク選び」です。
どんなに良い歌声や演奏でも、マイクの特性が合っていなければその魅力は半減してしまいます。
ここでは、ライブ現場での用途別マイク選びを、プロ音響の視点からわかりやすく解説します。
■ ボーカル用マイクの選び方
ライブで最も使用頻度が高いのが「ボーカルマイク」。
ここでは代表的な2つのタイプ、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いを理解することが大切です。
ShureのSM58を代表とするダイナミックマイクは、ライブステージの定番中の定番です。
頑丈で壊れにくく、湿気や衝撃に強いため、ツアーや屋外フェスなど過酷な環境でも安定した音を提供します。
特にロックやポップスのように音圧が高い現場では、ハウリング(音の回り込み)に強いダイナミックマイクが圧倒的に有利です。
一方で、音の繊細な表現や高域の伸びはやや苦手。
そのため、表現重視のアコースティック系やバラードには物足りなさを感じることもあります。
● コンデンサーハンドマイク:繊細で高解像度な音
NeumannのKMS105やShureのBeta87Aなどに代表されるコンデンサーハンドマイクは、声の息づかいやブレスまで細かく拾う繊細さが魅力です。
スタジオで録ったようなクリアな音質を、ライブでも再現できるのが最大の強みです。
ただし、コンデンサーマイクはファンタム電源が必要で、湿気や衝撃に弱いというデメリットもあります。
また感度が高いため、モニタースピーカーとの距離や角度を慎重に設定しないとハウリングが発生しやすくなります。
このため、ジャズやアコースティックライブ、ホールコンサートなど、比較的落ち着いた環境での使用に適しています。
楽器ごとのマイク選び
ボーカルだけでなく、各楽器にも最適なマイクがあります。
例えば、エレキギターアンプにはShure SM57やSennheiser e906などのダイナミックマイクが定番。
音圧に強く、中域のアタックをしっかり捉えてくれます。
アコースティックギターには、コンデンサーマイク(Neumann KM184やAT AE5400など)を使うと、
繊細な弦の響きを自然に再現できます。
ドラムには用途ごとに専用マイクがあり、スネアにはShure Beta57A、キックにはAKG D112など、
それぞれの帯域に合わせた設計が施されています。
ホーンやサックスなどの管楽器には、Sennheiser MD421のような大型ダイナミックマイクが定番です。
環境に合わせた選び方
マイクは「どこで使うか」によっても選び方が変わります。
- 屋外フェスや野外イベントでは、風や湿気に強いダイナミックマイク。
- ジャズクラブやアコースティックバーでは、コンデンサーの繊細な表現力が光ります。
- 配信ライブでは、ノイズの少ないコンデンサーマイクが好まれます。
- ツアーやリハーサルでは、扱いやすく耐久性のあるダイナミックタイプが最適です。
このように、「環境・音量・ジャンル」の3点を基準にマイクを選ぶことで、より自然で安定した音を得ることができます。
■ ワイヤードとワイヤレスの選択
ライブでは、ワイヤード(有線)かワイヤレス(無線)かも重要です。
ワイヤードマイクは電波の干渉がなく音質が安定しているため、音にこだわるボーカリストに好まれます。
一方、ステージ上を動き回るパフォーマーやダンサーには、ケーブルが邪魔にならないワイヤレスマイクが便利です。
最近ではワイヤレスでも高音質なモデルが増えており、プロの現場でも多く使われています。
■ ジャンル別おすすめマイク参考例
- ロック・ポップス:Shure Beta58A、Sennheiser e935
- ジャズ・バラード:Neumann KMS105、Shure Beta87A
- R&B・ソウル:AKG C5、Lewitt MTP940CM
- アコースティック/フォーク:Audio-Technica AE5400、Sennheiser e965
ジャンルによって、求める「音の太さ」「抜け」「柔らかさ」が変わるため、
それぞれに合ったマイクを選ぶのが理想です。
マイクは「音を拾う装置」ではなく、ボーカリストの声を楽器として形にする道具です。
どんなマイクを選ぶかで、同じ声でも印象がまったく変わります。
ライブでは、環境やジャンル、そして自分の表現スタイルに合わせて最適なマイクを選ぶことが、
最高のパフォーマンスにつながります。
初心者であれば、まずはダイナミックマイクを1本手に入れてライブ慣れし、次にコンデンサーハンドマイクを導入して音の世界を広げるのがおすすめです。
「どんなマイクが自分の声を一番輝かせるのか?」
それを探す過程こそが、ボーカリストの成長の証といえるでしょう。
🌌 ライブ録音で真価を発揮する“無指向性マイク”という選択
ここからは少し視点を変えて、「ライブを録音する側」から見てみましょう。
ライブ録音というのは、当スタジオが最も得意とするところであり、当スタジオの姉妹サイト、オーディオアカデミーでは金田式バランス電流伝送DC録音のご依頼を受け付けています。
PA用マイクは観客に音を届けるために“狭い範囲”を狙って拾う指向性マイクが主流ですが、録音においては“空間そのもの”をどう捉えるかが重要になります。
そのときに活躍するのが、無指向性マイク+AB方式という組み合わせです。
さて、当スタジオでは、ライブ関係者の方が気軽にライブ録音をしてほしいと思っています。
金田式DC録音は特別なスキルが必要ですのでご依頼いただくしかありませんが、一般的な高音質録音であれば現代では32bit技術もあり、後述しますマイクロフォンを導入するだけで誰でも簡単に録音することができます。
🎧 AB方式とは?空間を立体的に再現する録音技法
AB方式とは、2本の無指向性マイクを一定距離(通常は20〜60cm)離して配置し、左右の時間差によって自然な空間の広がりを再現する手法です。
この方式では、ステージ上だけでなく会場全体の空気や観客の反応、リバーブ感までもが生々しく記録されます。
結果として、録音を再生したときにまるで会場にいるかのような臨場感が再現されます。
🏛️ ライブPAと録音マイクの違いを理解する
| 項目 | PAマイク(拡声) | 録音マイク(収録) |
|---|---|---|
| 目的 | 音を届ける | 音を残す |
| 指向性 | 強い(単一指向) | 状況に応じて |
| 配置 | ステージ上 | ステージ・会場・ホール中央 |
| 音質傾向 | 近接感・明瞭度重視 | 空間性・自然さ重視 |
この違いを理解した上でマイクを選ぶと、「聴かせる音」と「記録する音」の両方がバランスよく仕上がります。
🎵 まとめ:ライブでは“用途別”、録音では“目的別”にマイクを選ぼう
- ステージでの歌や演奏を届けるなら ダイナミックマイク
- 空間全体の響きを残したいなら 無指向性AB方式マイク
- そしてその両方をバランスよく活かすのが、音づくりの本質です。
Kotaro Studioでは、「空気を録る」ためのマイク設計を通じて、あなたのライブの“その瞬間”を永遠に残すお手伝いをしています。