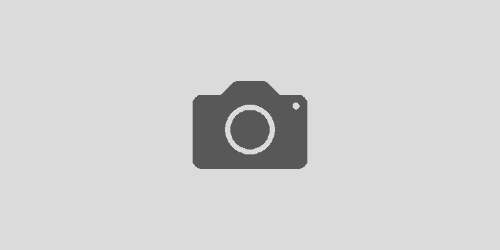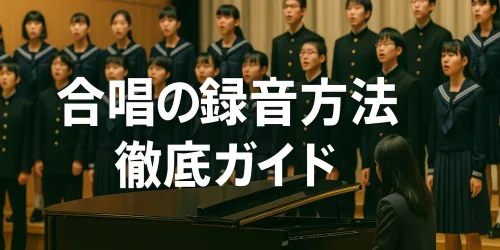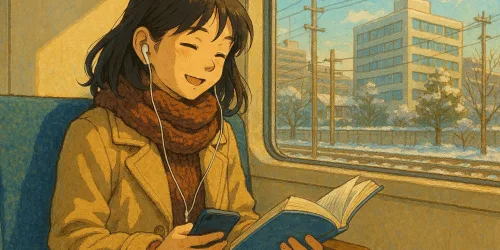録音した音源を再生するとスピーカーからジリジリ音?原因解説とAudacity, Logicでそれぞれノイズ対策を徹底解説

この記事の目次
SpotifyやYouTube、テレビの音声は問題ないのに、自分で録音した音源をスピーカーで再生するとジリジリとしたノイズを感じる…。
この現象は、実は多くの録音愛好家・初心者エンジニアが経験するものです。
結論から言うと、原因は「録音素材の周波数特性とスピーカーの共振がぶつかっている」ことがほとんどです。
スピーカーが悪いわけでも、録音機材、マイクが壊れているわけでもありませんのでご安心ください。

この記事を担当:朝比奈幸太郎
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイク技術を学び帰国
帰国後、金田式DC録音専門レーベル”タイムマシンレコード”て音響を学ぶ
独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース
その後写真・映像スタジオで音響担当を経験、写真を学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、音楽家, 音響エンジニア,として活動
五島昭彦氏より金田式DC録音の技術を承継中
当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。
♪この記事には広告リンクを含みます♪

【さらなる専門家の監修】録音エンジニア:五島昭彦
学生時代に金田明彦氏に弟子入り。
ワンポイント録音の魅力に取り憑かれ、Panasonic半導体部門を経て、退職後金田式DC録音の専門スタジオ:タイムマシンレコードを設立。
ジャズは北欧系アーティストを中心に様々な美しい旋律を録音。
クラシック関係は国内外の様々なアーティストのレコーディングを担当しており、民族音楽にも精通。
現在は金田式DC録音のDSDレコーディングを中心にアコースティック楽器の収録を軸に活動中。
世界で唯一、金田明彦氏直系の弟子であり、金田明彦氏自らが手がけた金田式DC録音システムを使用している。
🧩 原因①:無指向性マイクの「高域ピーク」
無指向性マイクは音を360度から拾うため、空間の反射音や高域のエネルギーが過剰に録音されやすい特性があります。
特にAB方式(左右にマイクを離した録音)は、マイク間の位相差によって5kHz〜10kHz帯に干渉ピークが生まれ、耳障りな「ジリジリ成分」が強調される傾向があります。
🎚️ 原因②:12cmフルレンジスピーカーのブレークアップ
フルレンジユニットを使っている場合にこのような状況が発生しやすいです。
例えば筆者の持ち運び用(外でマスタリングするスピーカー)は12cmフルレンジユニットに、ロシアンバーチの密閉エンクロージャーを使っていますが、12cmの場合一般的に7kHz〜10kHz付近でコーンが共振(ブレークアップ)します。
録音素材がその帯域にエネルギーを多く含んでいると、コーン紙が振動しすぎて「ジリジリ」や「シャリシャリ」といったノイズを生み出します。
これはスピーカーの構造的限界による現象であり、アンプや配線の問題ではありません。
🎛️ 原因③:商業音源には「音声編集の魔法」がある
Spotifyやジャズアルバムの音源では、高域をなめらかに整えるマスタリング処理が施されています。
代表的なのが以下のような処理になります。
- De-esser:6〜10kHz帯をダイナミックに抑える
- Dynamic EQ:高域が出過ぎた時だけ軽くカット
- マルチバンドコンプ:高域を全体的に均す
一方、自分の録音素材は「撮って出し」状態のため、耳に刺さる帯域がそのまま再生されてしまいます。
もちろん、これも解決策がありますので安心してください。
🧰 解決策①:音声編集でノイズを抑える
一般的に商業マスタリングで使われるプラグインには以下のようなものがあります。
| プラグイン名 | 用途 | 推奨設定帯域 |
|---|---|---|
| FabFilter Pro-Q 3 | Dynamic EQ | 6〜10kHz、−3dB |
| TDR Nova | De-esser | 7kHz中心、Q=2.5 |
| Oeksound Soothe 2 | 共鳴除去 | 5〜12kHz範囲で自動調整 |
| Waves C4 | マルチバンドコンプ | 高域バンドに軽い圧縮 |
EQで抑えることもできますので、無料で使えるAudacityでも十分対応可能です。
🎧 Audacityだけでの解決
問題帯域を「見える化」する(スペクトル解析)
Audacityで使う機能:
- 「プロットスペクトラム(Plot Spectrum)」
- スペクトログラム表示(トラックの表示モード変更)
やること(概要):
- 問題の箇所を選択して周波数解析
- 5〜12kHz付近の山・ピークをチェック
- どの辺りをEQで触るかの“あたり”をつける
次にEQ(Filter Curve EQ)で高域のジリジリ帯域をカット、6〜10kHz周辺のエネルギーを数dBだけ抑えて、スピーカーのコーンが鳴き過ぎないようにしましょう。
Audacityで使う機能:
- 「Filter Curve EQ」(旧名称:Equalization)
やること(概要):
- 7〜9kHz付近にピークカット(ベル型)
- 必要に応じて12kHz以降を軽くロールオフ
- かけ過ぎず、2〜4dB程度から始める
他にも簡易De-Esser処理(高域だけを狙った抑え込み)として、EQだけでは足りない場合に、ジリジリが出た瞬間だけ高域を抑える“擬似De-Esser”処理を行う方法もあります。
Audacityで使う機能/方法:
- トラックを複製して「高域専用トラック」を作る
- 高域だけを残すEQ(ハイパス+シェルフ)
- その高域トラックにコンプレッサーを強めにかける
- 最後に高域トラックのボリュームをミックスで調整
※Audacityは標準でDe-Esserを持たないため「擬似マルチバンド・コンプ的なワークフロー」で実現するイメージ。
ピークを抑えて耳障りな瞬間をならす(Limiter/Compressor)スピーカーが一瞬だけ「ビッ」と鳴くようなピークを、LimiterとCompressorで丸める方法もあります。
Audacityで使う機能:
- 「Limiter」
- 「Compressor」
やること(概要):
まずLimiterでピークを一定レベルに収める
- その後、Compressorで全体のダイナミクスを少し整える
- これによって、コーンが暴れやすい瞬間のエネルギーをコントロール
録音全体の“キツさ”を和らげる全体トーン調整(中高域の微調整)として、耳に刺さる中高域(2〜5kHz)も合わせて軽く調整し、聴き疲れしないスピーカー再生用のトーンに整える方法も試してみてください。
Audacityで使う機能:
- 「Filter Curve EQ」
やること(概要):
- 3〜4kHzを1〜2dB程度カットしてみる
- 逆に200〜400Hzあたりをごく軽く持ち上げて“肉付け”する
- 「ノイズっぽさ」が実は中域の固さとセットで聞こえている場合も多いので、トータルで調整
カテゴリー7:外部無料プラグイン(VST)をAudacityに追加して精密処理
目的:
Audacity標準EQだけでは物足りない場合に、無料のプラグインでDynamic EQやより自然な高域処理を行う。
代表的なプラグイン例:
- TDR Nova(Dynamic EQ/De-Esser的にも使える)
- Lisp(De-Esser) などのフリーDe-Esser
やること(概要):
- AudacityのVSTプラグインフォルダにインストール
- 6〜10kHzあたりにDynamic EQを設定し、ジリジリが出た時だけ抑制
- 標準機能よりも自然で透明度の高い「音声編集 ノイズ対策」が可能になる
🎚️ Logic Proでの例
ここからはMac派の方に便利で有料のアプリであるロジックでの処理方法を見ていきます。
Logic Pro の内蔵プラグインだけで、録音した音源のジリジリ・シャリシャリを抑えるための
プラグインと手順を確認していきましょう。
基本的にはこんな感じです👇
Channel EQ → DeEsser 2 → Multipressor(必要なら) → Compressor → Adaptive Limiter
順番にいきます。
① Channel EQで「ノイズ帯域を見つけて少し削る」
Audacityでも紹介しました。
EQで削る方法です。
- ジリジリが出ている帯域(多くは 6〜10kHz 周辺)を特定し、2〜4dBほどカットしてスピーカーのコーン鳴きを減らす。
プラグインはChannel EQ(チャンネルEQ)を使用してください。
- トラックに録音データを読み込む
- 新規プロジェクトを作成 → 録音したオーディオファイルをトラックにドラッグ&ドロップ。
- 一番気になる「ジリジリ箇所」をループ再生
- 波形を見て、問題を感じる部分を選択 → ループマークを設定して繰り返し再生。
- Channel EQをインサート
- 対象トラックのインサートスロット →
「EQ」→「Channel EQ」を選択。 - EQウインドウ右上の Analyzer(解析)を ON にする。
- 対象トラックのインサートスロット →
- ジリジリが鳴る瞬間のスペクトラムを観察
- ループ再生しながら、ノイズが強く聴こえるタイミングで Analyzer をチェック。
- 多くの場合、6〜10kHz辺りに急に飛び出たピークが見える。
- ピーキングEQでその帯域を狙い撃ち
- 例:7.5 kHz あたりのバンドを1つ有効化。
- Qを 2.0〜3.0(やや細め) に設定。
- まずは +6dB くらい持ち上げて「あえてうるさく」してみる。
- → ジリジリが強調されるなら、そこが“犯人帯域”。
- 確認できたら、−3〜−4dB程度のカットに変更。
- 必要なら12kHz以上を軽くロールオフ
- 一番右のハイシェルフorローパスを使って、
12kHzあたりから −2〜−3dBくらい下げてみる。 - 「少し地味だな」と思う一歩手前で止めるのがコツ。
- 一番右のハイシェルフorローパスを使って、
② DeEsser 2で「ジリジリが出た瞬間だけ」抑える
- 常時EQで削りすぎると音が痩せるので、
ジリッと出た瞬間だけ高域を抑える(ダイナミックなノイズ対策)。
使うプラグインとしては、DeEsser 2を使います。
- Channel EQの次のスロットにDeEsser 2を挿入
- インサート → 「Dynamics」 → 「DeEsser 2」。
- Modeを確認
- 「Split」モード or 「Wide」モード。
- まずは自然になりやすい Split から試すと分かりやすい。
- 検出する周波数帯を設定
- 「Frequency」ノブを、さっき EQ で見つけた帯域へ。
- 例:7〜8kHz付近。
- 「Monitor(Listen)」ボタンがあればONにして「どの成分だけを聞いているか」確認。
- 「Frequency」ノブを、さっき EQ で見つけた帯域へ。
- Threshold(しきい値)を調整
- 再生しながら、ジリジリが鳴る場所で Threshold を少しずつ下げる。
- 「Reduction(減衰量)」メーターが −2〜−4dB くらい軽く動く程度に。
- やりすぎると音がこもるので、「効いてるな」手前で止める。
- 再生しながらバイパス比較
- DeEsser 2をON/OFFしながら、
- ジリジリが減ったか?
- 音楽的な輝きまで消えていないか?
- をチェックする。
- DeEsser 2をON/OFFしながら、
③ Multipressorで「高域だけコンプ」する(必要に応じて)
- 全体として高域が少し暴れ気味な録音の場合、
5kHz以上にだけ優しくコンプをかけて“ならす”。
使うプラグインはMultipressor(マルチバンドコンプ)です。
- DeEsser 2の後ろにMultipressorを挿入
- 「Dynamics」→「Multipressor」を選択。
- バンド設定
- デフォルトで4バンドあるので、一番上のバンドを高域専用にする。
- 例:Band4 を 5kHz〜20kHzに設定。
- それ以外のバンドは、最初はバイパスしておいてOK(あるいはほぼ何もしない設定に)。
- デフォルトで4バンドあるので、一番上のバンドを高域専用にする。
- 高域バンドのコンプ設定
- Ratio:1.5〜2.0:1(軽め)
- Attack:5〜10ms 前後
- Release:60〜150ms くらい(音源に応じて調整)
- Threshold:ループ再生しながら、ジリジリが出るところで 少しだけ GR(ゲインリダクション)−2〜−3dB 程度 動くように。
- バンドのGainを微調整
- 高域を圧縮すると少し暗く聴こえるので、
- 必要なら Band4 の出力ゲインを +0.5〜+1dB 上げてバランスをとる。
- 高域を圧縮すると少し暗く聴こえるので、
- バイパスして比較試聴
- Multipressor ON/OFF で、
- 「耳に刺さる感じ」が和らいでいるか
- かつ、音楽の抜けが残っているか
- を確認する。
- Multipressor ON/OFF で、
④ Compressorで全体のダイナミクスを軽く整える
- 一瞬だけ大きく飛び出るトランジェントがスピーカーを揺さぶりすぎないように、
全体を軽くまとめる。
使うプラグインはCompressorです。
- Multipressorの後にCompressorを挿入
- 「Dynamics」→「Compressor」。
- タイプ選び
- 「Platinum Digital」や「Studio VCA」など、癖が少ないモデルからスタート。
- 基本設定の目安
- Ratio:1.5〜2.0:1
- Attack:20〜30ms(トランジェントはある程度残す)
- Release:100〜200ms
- Knee:ソフト寄り(デフォルトでOKなことが多い)
- Thresholdを調整
- ループ再生しながら、
GRメーターが−1〜−3dB程度動くくらいにThresholdを下げていく。 - 強くかける必要はなく、「まとめるための軽い接着剤」イメージ。
- ループ再生しながら、
- Gainを調整
- Makeup Gainを使って、コンプ後の音量がコンプ前と大体同じになるように合わせる。
- 音量差による「大きいほうが良く聴こえるバイアス」を避けるため。
⑤ Adaptive Limiterでピークを抑えてスピーカー保護+音量調整
- 出力のピークを安全なレベルに抑えつつ、
再生時の音量を上げてもスピーカーが破綻しにくい状態にする。
使うプラグインとしては、Adaptive Limiter(または Limiter)です。
- ステレオアウト(Master)にAdaptive Limiterを挿入
- Stereo Out のインサート → 「Dynamics」→「Adaptive Limiter」。
- Out Ceilingを設定
- 例:−0.5dB に設定(クリップしにくくするため)。
- Input Gainを調整
- 再生しながら Input Gain を少しずつ上げて、
Reduction(リダクション)が −1〜−3dBくらいになるように。 - これ以上強くかけると不自然に感じやすいので、音源のジャンルにより調整。
- 再生しながら Input Gain を少しずつ上げて、
- 再生環境での最終チェック
- 実際の12cmフルレンジ+スーパーツイーターのシステムで再生し、
- ジリジリ・ビリビリが出ないか
- 長時間聴いても耳が疲れないか
- を確認する。
- 実際の12cmフルレンジ+スーパーツイーターのシステムで再生し、
Logic内蔵だけでできる「録音ノイズ対策」
- Channel EQ
→ 問題帯域(多くは6〜10kHz)を見つけて2〜4dBカット - DeEsser 2
→ ジリジリが出た瞬間だけ高域を抑える - Multipressor(必要に応じて)
→ 5kHz以上のバンドを軽くコンプして高域全体を“ならす” - Compressor
→ 全体のダイナミクスを軽く整えて飛び出すピークを抑える - Adaptive Limiter
→ 最終的なピーク管理と音量確保、スピーカー保護
🧠 解決策②:スピーカー側の共鳴を軽減させる
スピーカーの物理的特性に合わせた軽い補正も効果的です。
EQ設定例(パラメトリックEQ)
| 周波数 | Q値 | ゲイン |
|---|---|---|
| 7.5 kHz | 3.0 | −2.5 dB |
| 10 kHz | 2.5 | −1.5 dB |
もしDSPを使える場合は、12kHz以降を−3dB程度ロールオフさせるとより自然になります。
🧾 まとめ:録音ノイズは「編集で整う」「原因は自然」
録音した音源がスピーカーでノイズっぽく感じるのは、
「録音素材の高域バランス」と「スピーカーの共振」がぶつかる、自然な物理現象です。
✅ 対策のポイント:
- 高域6〜10kHzを軽く処理(Dynamic EQ / De-esser)
- スピーカーのEQで共鳴を−2〜3dB調整
- 録音位置・距離・角度を見直す
これだけで「ジリジリ」「シャリシャリ」が驚くほど消えます。