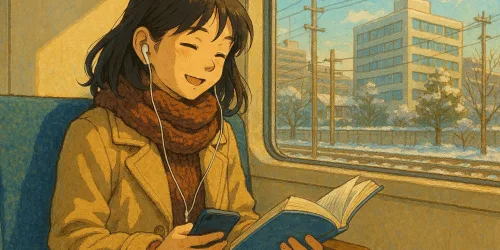【音声編集】Audacityでノイズ除去を徹底ガイド|イコライザーを使ったノイズ除去まで
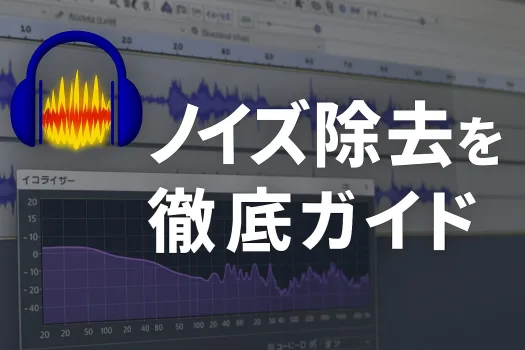
この記事の目次
音声編集をしていて特に気になるのはノイズの除去ではないでしょうか?
もちろんノイズをどう定義するのか?というのは非常に難しいところだと思います。
音そのものをポジティブに捉えるのか?ネガティブに捉えるのか?によってもノイズの定義は大きく変わります。
例えば、電車の音、これを狙って録音する人もいれば、ノイズだと感じる人もいます。
また、誰かの話し声もノイズだという人もいれば、筆者などは、シークエンスの要素、つまりその収録、録音のストーリーの一部であると考えます。
ですので、一言にノイズ除去といっても、人の数だけあるノイズはあるといっても過言ではありませんので、難しいところがあります。
今回の記事ではまず、ノイズをどのように定義するのか?今一度考えてみるきっかけにしてもらいたく一般的なAudacityでのやり方、また、もしかしたら今ノイズだと思ってるその要素はイコライザーで簡単に消せるかもしれないというお話をお届けします。

この記事を担当:朝比奈幸太郎
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイク技術を学び帰国
帰国後、金田式DC録音専門レーベル”タイムマシンレコード”て音響を学ぶ
独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース
その後写真・映像スタジオで音響担当を経験、写真を学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、音楽家, 音響エンジニア,として活動
五島昭彦氏より金田式DC録音の技術を承継中
当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。
♪この記事には広告リンクを含みます♪
Audacityでノイズ除去を行う基本手順
一般的に音声編集ソフトにはそれぞれノイズの除去機能が備わっています。
昨今のソフトであれば基本的に50歩100歩のところがあります。
Audacityには「ノイズの除去と修復」→「ノイズの除去」というエフェクトが標準搭載されており、音声ファイル内の定常的なノイズを減らすことができます。
以下の手順で行います。
- ノイズプロファイルの取得
- 波形の中からノイズだけが鳴っている部分(0.5〜2秒程度、人の声や他の音が入っていない区間)をドラッグして選択します。
- メニューの「エフェクト」→「ノイズの除去と修復」→「ノイズの除去」を開き、「ノイズプロファイルを取得」をクリックします。これによりAudacityがどの音をノイズとして扱うかを学習します。
- 音声全体へのノイズ除去適用
- 次に、Ctrl + A で波形全体を選択します。
- 再び「エフェクト」→「ノイズの除去と修復」→「ノイズの除去」を開き、ノイズ除去の設定画面を表示します。
- 「ノイズ除去(dB)」はノイズ低減の強さを示し、数値が大きいほどノイズが強く消えますが音質が劣化しやすくなります。
- 「感度」は何をノイズと判定するかの範囲で、数値を上げるほど多くの音をノイズとみなします。
- 「周波数のスムージング(バンド)」はノイズ低減後の音の自然さに関わるもので、数値を上げるほどなめらかになります。
- プレビューで確認しながら設定を調整し、自然な音質を保てるようにしてください。ノイズ除去を強くかけすぎると声がこもるので注意が必要です。
イコライザーでノイズを除去する方法
ノイズの中には一定の周波数に集中しているものがあり、イコライザーを使ってその帯域を減衰させることでノイズを目立たなくできます。
様々なハンディレコーダーに搭載されているローカットもノイズ除去の機能の一つであると言えます。
イコライザーは周波数毎の音量を増減できるエフェクターで、残したい音とノイズが重なっている場合にも有効です。
ノイズの周波数を特定する
- ノイズが常に鳴り続けている場合は、そのノイズがどの周波数に分布しているかを確認します。Audacityの「スペクトラム表示」やアナライザー機能を使ってピークが立っている周波数を探します。
- ノイズの周波数が分かったら、その周波数を中心にイコライザーでカットします。例えば、ツキシマブログの例では125 Hz付近にノイズが集中していたため、イコライザーの周波数を125 Hz、Q幅(バンド幅)を5、ゲインを−20 dBに設定してカットすることでナレーションには影響せずノイズを除去しています。
AudacityでのEQ処理手順
Audacityには「Filter Curve EQ」と「Graphic EQ」というイコライザーエフェクトがあります。
以下は基本的な手順です。
- 編集したい音声を選択した状態でメニューの「エフェクト」→「Filter Curve EQ」または「Graphic EQ」を開きます。
- ノイズの周波数を目安に、Filter Curveならポイントを追加してその周波数を大きく下げるカーブを描きます。Graphic EQなら該当する周波数帯(例:100 Hz〜130 Hzなど)のスライダーを下げます。
- Q値(帯域幅)を狭くすることで、目的の周波数のみをピンポイントで減衰できます。広くしすぎると音楽や声の重要な帯域にも影響するため注意してください。
- カット量は必要最小限に抑えましょう。−3 dB〜−20 dB程度からプレビューし、ノイズが目立たなくなるところで止めます。
- ノイズの帯域が複数ある場合は複数ポイントを設定してそれぞれの帯域を少しずつカットします。
イコライザーを使うメリット・注意点
- イコライザーは特定の周波数のノイズを狙って減衰できるため、ノイズとメインの音が重なっている場合でも音質を保ちながらノイズを軽減できます。
- 周波数が一点に集中しているノイズ(電源ハムや機械ノイズなど)には特に有効です。
- 逆に、広範囲の周波数にわたるノイズや時間的に変化するノイズには、イコライザーだけでは十分な効果が得られない場合があります。その場合は専用のノイズ除去プラグインや「ノイズの除去」機能と併用することを検討しましょう。
まとめ
Audacityには強力なノイズ除去機能があり、ノイズプロファイルを取得して不要な雑音を減らすことができます。
さらに、イコライザーを使って特定の周波数に集中したノイズを減衰させることで、メインの音を守りながらノイズを目立たなくできます。
ノイズの種類や状況に応じて適切な方法を選択し、プレビューを重ねながら自然な音質を追求してください。