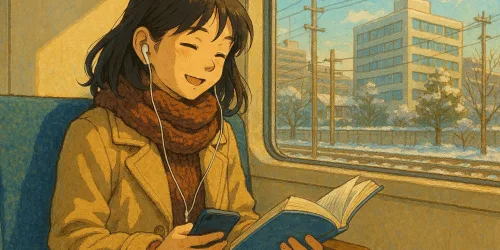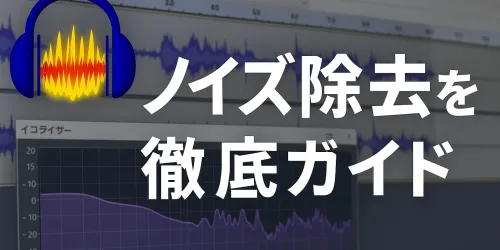Audacityで音声編集のやり方を徹底解説:基本からノーマライズまで

この記事の目次
Audacityを始めたばかりの方は、録音した音声をどう扱えば良いのか迷うことが多いでしょう。
特に無指向性ステレオAB方式で収録したデータは奥行き感や広がりが豊かな一方で、バランス調整や音量の統一に戸惑いがちです。
本記事では、音声ファイルの読み込みからノーマライズまでの基本操作を、初心者でも実践できるようにわかりやすく解説します。
この記事はすべてステレオAB方式録音を前提にしており、モノラルを想定していません。
Audacityのインターフェースに慣れていない方でも、手順を追うことで確実に音質を向上させるコツが理解できます。
編集作業のストレスを減らし、本来のクリエイティブな作業に集中できるようサポートします。

この記事を担当:朝比奈幸太郎
1986年生まれ
音大卒業後日本、スウェーデン、ドイツにて音楽活動
ドイツで「ピアノとコントラバスのためのソナタ」をリリースし、ステファン・デザイアーからマルチマイク技術を学び帰国
帰国後、金田式DC録音専門レーベル”タイムマシンレコード”て音響を学ぶ
独立後芸術工房Pinocoaを結成しアルゼンチンタンゴ音楽を専門にプロデュース
その後写真・映像スタジオで音響担当を経験、写真を学ぶ
現在はヒーリングサウンド専門の音楽ブランド[Curanz Sounds]を立ち上げ、音楽家, 音響エンジニア,として活動
五島昭彦氏より金田式DC録音の技術を承継中
当サイトでは音響エンジニアとしての経験、写真スタジオで学んだ経験を活かし、制作機材の解説や紹介をしています。
♪この記事には広告リンクを含みます♪
Audacityでの音声編集やり方手順
Audacityを起動したら、まず音声ファイルを読み込みます。
メニューバーから「ファイル>開く」または「ファイル>取り込み>音声の取り込み」で録音したデータを選択します。
無指向性ステレオAB方式で録音した左右2チャンネルは、自動的にステレオトラックとして表示されます。
次に、不要な部分のトリミングやフェードイン/アウトを行いましょう。
Macでは⌘+A、WindowsではCtrl+Aでトラック全体を選択できます。
ノーマライズの手順は簡単です。
ノーマライズしたい範囲または全体を選択し、メニューバーの「エフェクト>音量と圧縮>ノーマライズ」をクリックします。
表示されるダイアログで「DCオフセットの削除」「最大振幅をノーマライズ」「ステレオチャンネルごとにノーマライズ」を設定し、デフォルトの振幅値(当スタジオでは-0.1 dB)を確認したら「OK」を押します。
これで左右チャンネルのバランスを保ちながら音量が適正化されます。
なお、音量をさらに上げたい場合は同じ「エフェクト」メニューの「増幅」を使い、クリッピングを防ぐために「クリッピングを許可しない」にチェックを入れてください。
ラウドネス調整のやり方【Audacity】
ラウドネスとは「人が感じる音の大きさ」を統一するための調整です。
単純に波形の振幅をそろえるノーマライズとは異なり、周波数特性や時間変化を考慮して聴感上の音量を整えるのがラウドネスです。
ラウドネス調整の手順
- 編集したいトラックを選択
- メニューから [エフェクト]→[ラウドネスの正規化(Loudness Normalization)] を選択
- 「目標ラウドネス(LUFS)」に数値を入力
→ 一般的には −16 LUFS(YouTubeなど配信用) や −23 LUFS(放送基準) を目安にします - 「RMSノーマライズ」を選ぶことで従来の平均音量ベースの処理も可能
- OKをクリックして適用
ラウドネス設定の数値基準
配信用音源なら −14〜−16 LUFS に統一するのが自然です。
クラシックや自然音などダイナミックレンジを保ちたい場合は −18 LUFS 程度に留めましょう。
ラウドネスとノーマライズの違いと使い分け
| 項目 | ノーマライズ | ラウドネス |
|---|---|---|
| 基準 | 波形の最大振幅 | 聴感上の音量(LUFS基準) |
| 処理方法 | ピークを基準に全体をスケーリング | 周波数・時間特性を加味 |
| 主な用途 | 録音時の音量揃え | 配信・放送・マスタリング |
| メリット | シンプルで高速 | 聴感上の自然な統一 |
| デメリット | 聴感上の差が残る | 計算負荷がやや高い |
使い分けの目安
- 録音素材の編集中(整音段階) → ノーマライズ
- 最終出力前(配信用・マスタリング段階) → ラウドネス正規化
✂️ 波形データのカット(不要部分の削除)
カットの手順
- トラック内で削除したい範囲をドラッグ選択
- Deleteキー または 編集 → 切り取り(⌘X) を実行
- カット後、トラック → オーディオの結合 で不要な隙間を詰める
- ズームツール(🔍)を使って波形を拡大し、クリックノイズやブツ切りを確認
- 必要に応じて「フェードイン/フェードアウト」で自然に繋げる
💡補足
ナレーションなどの「間」を整える際は、タイムシフトツール(↔️アイコン) を活用して自然な間を保ちましょう。
編集後のチェックポイント
- ノーマライズ → −1.0 dB 以内を目安
- ラウドネス正規化 → 目的に応じたLUFS値
- クリックノイズ → 「効果音除去」や「スムーズ化」で除去
- 全体の音質確認 → ヘッドホンとスピーカーで両方チェック
よくあるトラブルと注意点
左右バランスの崩れ・ピーク超過対策
ステレオAB録音では、左右マイクの距離や高さが揃っていないとバランスが崩れ、片側が強調されることがあります。
通常はそのようなことが起こらないように録音するのがベストですし、あえて片側に寄っているのも録音意図の可能性がありますので、波形だけでバランスを調整しないということが大切。
録音時にはマイク間の距離と角度を揃え、録音後はAudacityで左右レベルメーターを確認しながら必要に応じて増幅やパンを微調整しましょう。
また、ノーマライズや増幅処理でピークが0 dBを超えると歪みが発生します。
Audacityの増幅ダイアログでは「クリッピングを許可しない」にチェックを入れることで安全なレベルに抑えられます。
MS変換やモノ化との違い・比較
MS変換はMid-Side方式で録音されたデータをステレオに展開する技術で、中心成分と側成分を独立して調整できます。
一方、ステレオAB方式は2本の無指向性マイクの自然なタイム差と音量差を利用するため、MS変換や後処理によるモノラル化よりも自然な空間表現が得られます。
モノラル化は左右チャンネルを合成して定位を中央に集める処理で、不要な位相干渉を避けられますが、臨場感や広がりは失われます。用途に応じて選択しましょう。
🧠 まとめ
Audacityの音声編集で重要なのは、
1️⃣ 波形編集による不要部分の整理
2️⃣ ノーマライズによる音量の基礎統一
3️⃣ ラウドネス正規化による聴感上の最終調整
この3ステップを意識することで、配信・ナレーション・音楽制作すべてで安定した音質を実現できます。